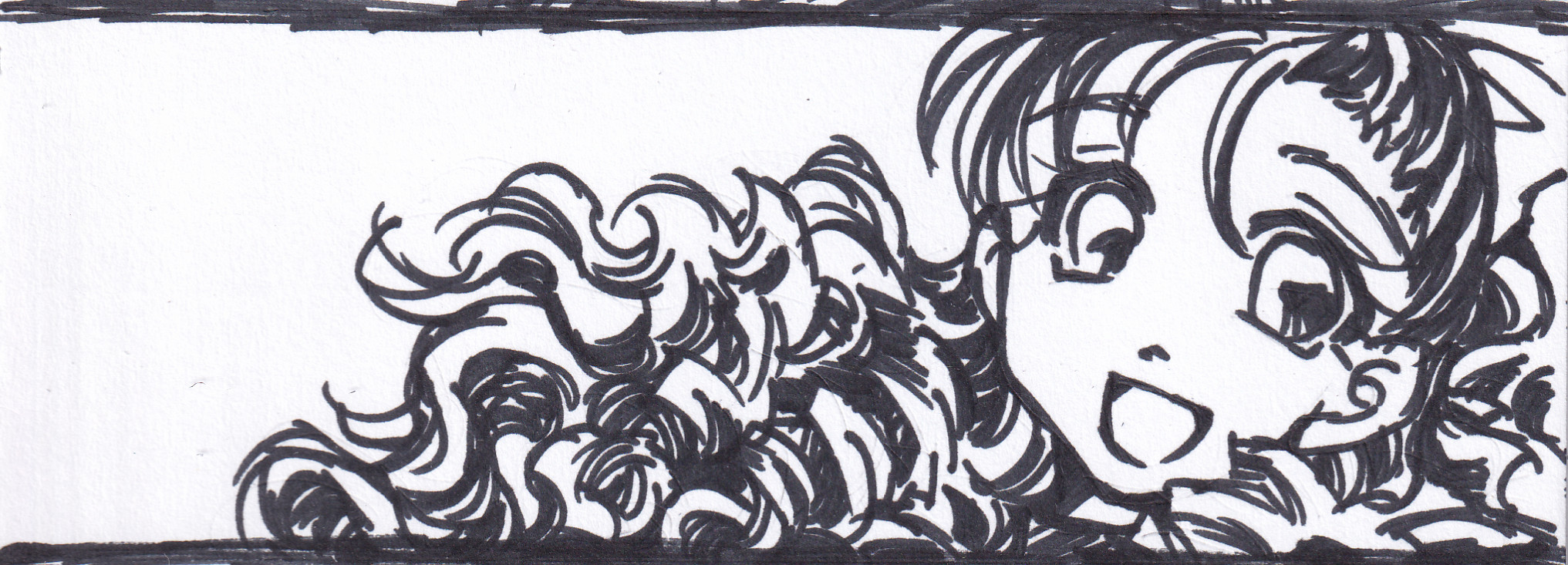
Mirca Arredina
ずっと会いたかった。 あこがれのあなたと。 恋焦がれたあなたと。 手の届かない場所にいることはわかってる。 その場所に行くためには、たくさんの努力が必要なことも。 けど。 わたしは、何一つあきらめない。
朗報
「えっ?!」
がば。
手紙を握りしめたまま、ミルカは勢いよくベッドから起き上がる。
そこに書かれていた、なかば信じられない内容に、彼女は改めて手紙を握りしめ、食い入るようにその文面を見つめた。
『継承祭で、魔術師ギルドの手伝いをすることになったよ。だから、期間中はヴィーダに滞在することになると思う。手伝いをするから一緒にお祭りを回ったりはできないと思うけれど、どこかで会えるといいね』
「夢…じゃないわよね」
ぐに。
頬をつねってみるが、ちゃんと痛い。
「夢じゃない……!」
ひりひりする頬を抑えながら、ミルカは目を輝かせた。
「フィズに会える……!」
フィズ・ダイナ・シーヴァン。
ミルカが通うこのフェアルーフ王立魔導士養成学校の元生徒であり、ミルカの恋人だ。今はマヒンダの魔道学校に通っていて、彼女とはこうして手紙でのやり取りを交わすのみの、いわゆる遠距離恋愛となっている。
その恋人が、継承祭のイベントの手伝いとして、マヒンダからフェアルーフに帰ってくるのだ。
「カイ!聞いて!」
「はい?」
ちょうど部屋に帰ってきたルームメイトに、おかえりの挨拶もなく詰め寄る。
カイはミルカの勢いに面食らった様子で答えた。
「なに、どうしたの」
「フィズが帰ってくるんですって!」
「マジで?なんで」
「継承祭で、魔術師ギルドのお手伝いをするんですって。期間中は滞在するらしいわ」
「へえ、よかったじゃん」
「でしょ!毎日がんばってるわたしへの神様のご褒美なんだわー!」
「邪魔が入らなければね」
「うっ……」
ぎくり。
意地悪く笑ったカイの言葉に、体を硬直させるミルカ。
そう。
こんなことは過去何度もあった。
フィズが帰ってくる。あるいは、フィズがいるマヒンダに行ける。
しかし、そのたびに邪魔が入るのだ。
彼の養母であり、そしてこのフェアルーフ王立魔導士養成学校の校長でもある、ミリーの手によって。
「それなのよねぇ……」
ミルカはため息をついた。
もちろん、ミリーも単なる意地悪だとか姑根性で邪魔をしているわけではない。
そもそもなぜ、元々はフェアルーフの学校にいたフィズが、マヒンダの学校に転校することになったのか。
元をただせばそれは、ひとえにミルカ本人が原因なのだ。
『あなたたちはね、相性が良すぎるの』
噛んで含めるように、ミリーは二人に告げた。
『ミルカちゃんは魔力が無いわけじゃない。むしろ逆。人の器には入りきらないほどの膨大な魔力があるの。だから、人の器で使おうとすると、魔力の出口に詰まって暴発しちゃうイメージかな。
でも、フィズがそばにいることで、ミルカちゃんの魔力の出口が大きく空くの。あなたの意志とは関係なくね。
だから、フィズがそばにいる時にだけ、あなたの魔法は成功するわけ』
『そう……なんですか』
『それ自体はとても喜ばしいことね。でも問題点が一つある。ただ一つの、そして致命的な問題点が』
『コントロールが効かない……ですか』
『その通り』
フィズが言い、そちらに向かって頷くミリー。
『コントロールの効かない魔法を放って、ターゲット以外の被害をもたらす可能性がある。ものだけの破壊で済めばいいわ。命を奪う可能性だってある。それは、校長として看過できる問題じゃないのよ』
ミリーはいつになく真剣な表情で、ゆっくりと二人に告げた。
『だから、ミルカちゃんが魔力をコントロールできるようになるまで、あなたたちは離れて暮らしなさい。これはお願いじゃない。命令よ』
「ミリー先生が何もしてこないわけがないわよねぇ…」
「そうだね、ギルドの手伝いならミリー先生だって知ってるだろうし」
魔術師ギルドの総評議長とミリーは旧知の間柄という話だ。当然、フィズの来訪の件もミリーに伝わっているだろう。
「でも、継承祭の時は学校もお休みでしょ?別に何も言われないんじゃない?」
「甘いわ…こういう時に限って遠くの土地へのお使いを頼まれたりするのよ…お使いに行ってる間にフィズとすれ違いになったりするんだわ…」
あんな思い出やこんな思い出がよみがえる。
「そういやそんなこともあったよね…けどさ、今までのそれって、今回みたいに事前にあいつが帰ってくるって連絡あったっけ?」
「……そういえば、無いわね」
「それって、帰ってくることを言わないようにって言われてたのもあったんじゃない?あんたたち、ほぼ毎日文通してるんだしさ、そういう予定があるなら言わないとかないじゃん」
「それは確かに」
「だったら、今回、事前にこうして知らせてきたってことはさ、ミリー先生から許可が出たってことなんじゃない?」
「ええええ、そうかなあ」
今までが今までなだけに疑惑のまなざしを向けるミルカ。
カイは肩をすくめた。
「さあ、本当のところは本人に聞かなきゃわからないけどさ。つか、本人に聞いてみたらいいんじゃない?」
「本人って」
「ミリー先生」
「ええええそんな藪をわざわざつつくようなことしたくないわよ!」
「藪から何か出てくるとは限らないじゃん」
「いや出てくる…ほぼ100%出てくる……」
「そもそも出すつもりならあんたが聞いても聞かなくても出るでしょ」
「そうなんだけどさぁ…なんか自分で引き金を引くのが嫌っていうか」
「あんたにしては珍しいね。当日まで悶々と悩むよりはいいでしょうに」
「わかってるんだけどー…!」
ぼふ。
枕に顔を埋めてもだえるミルカ。
結局、その日はああでもないこうでもないと言い合ったのみで、それ以降もミリーに自ら聞きに行くこともなく、かといってミリーに特段何か呼び出しを受けることもないまま、拍子抜けするほどあっさりと継承祭当日となった。
「おかしい…何もない…」
継承祭初日。
ヴィーダの街は早速かなりの賑わいを見せており、特にここバザールは盛況だ。国内外から訪れた様々な店が並び、多くの人々が行き交っている。
その賑わいの中を、ミルカは難しい顔をしてぶつぶつ呟きながら歩いていた。
となりを歩くカイが呆れた様子で肩をすくめる。
「何もないならいいじゃん、そんな辛気臭い顔してないで祭りを楽しみなよ」
「でもー」
「だからスパッと本人に聞けって言ったのに」
「だってー」
「はいでもでもだって終了!今度ミリー先生に会ったらあたしから聞くから!この話は終わり!」
「えええええ」
強引に話を終わらせてきたカイに、ミルカは不満というより純粋に驚きの声を上げた。
半眼で告げるカイ。
「悩んでも解決しないことを悩んでも時間の無駄!一緒に過ごしてるあたしにも失礼!わかったらお祭りを楽しむ!以上!」
「カイ…」
それが彼女なりの励ましであることに思い至り、ミルカはふっと肩の力を抜いて微笑んだ。
「…それもそうね!じゃあ、さっそくタビオカミルクティー飲みに行きましょ!」
「あたしあっちのでかい唐揚げ食べたい」
カイも何事もなかったかのように微笑んでミルカの話に乗り、二人は改めてバザールの喧騒の中へと足を踏み出した。
「いろいろあるのねえ…この辺は服とかを売ってるのかしら」
「そうみたいだねー」
念願のタピオカを飲みながら、あたりの店構えを見つつ言うミルカに、顔ほどもある大きな薄い唐揚げを食べながら興味なさそうに相槌を打つカイ。
彼女がファッションに興味がないのは織り込み済みなので特に気にすることもなく、ミルカは興味深げにあたりを見回した。
「見て、あっちは金細工ですって。すごーい、綺麗ね」
「へえ、珍しいね」
やはり気のない様子ではあるも、多少の興味はひかれたようにミルカの指さす方向に目をやるカイ。
机上に広げられたビロードの上に、大小さまざまな金細工が並べられている。先ほどちらりと聞こえた呼び込みの声からすると、フォラ・モントというところで作られた金細工であるようだ。
「…そうだな、黒髪に金細工は映えるな…女性用のイヤリングで良い奴はないか?」
「女性用のイヤリングか…」
今は店の前で興味深そうに品定めしている男性がいるため、店主はそちらと会話しているようだ。
「丸顔だから、尖ったのじゃなくて果物をあしらったようなだな」
「いやに具体的だな。兄さんの恋人か?」
「ん、まあ、そんなところ、か…?」
「果物か…可愛い感じなら、この辺の桃か…チェリーなんかもかわいいな。イチゴもいいだろ」
「なるほど…どれも甲乙つけがたいな……」
男性はかなり熱心に店主と会話している。彼が買い物を終えたら自分も見てみようか、と思っていると。
「……ん?」
よくよく見れば、男性の後ろ姿に見覚えがある。
ゆるくウェーブがかかった黒髪に、このあたりではあまり見かけないターバン姿。
「……あれ、もしかしてニクス?」
名を呼ぶと、男性は驚いて振り返った。
「ミルカじゃないか。久しぶりだな」
想定通りの人物であったことに破願して彼に駆け寄るミルカ。
「お久しぶり!今はヴィーダにいるの?」
「ああ、つい最近ウェルドに来てな、継承祭ってのやってるっていうからヴィーダにも来てみたんだ」
ニクスと呼んだ彼は笑顔でそう言い、改めてあたりを見渡す。
「賑わってるな」
「そうね、ここ最近で一番のお祭り騒ぎよ」
と、そこに後ろからカイがひょいと顔を出した。
「ミルカ、知り合い?」
「あ、うん。前にほら、ナノクニに行った時に一緒だった冒険者の…」
「ニクスだ。ミルカの友達か?」
ニクスが軽く挨拶をすると、カイも気さくに微笑む。
「そう。カイだよ。よろしくね」
「よろしく」
軽く握手を交わしたところで、カイの表情がくわっと驚きに変わった。
「ニクス……ってああ!あかりの彼氏だっけ?!繋がったわ」
「あかりを知ってるのか?」
「わたしたち、クラスメイトだもの」
その問いにミルカが答えると、ニクスはああ、と思い出したように頷いた。
「そういえば、魔法学校に通ってるって言ってたな……」
「その『そういえば』はわたしにかかるのかしら、あかりにかかるのかしら」
ニヤニヤと冷やかすような笑みを向けるミルカ。
あかり、とは。
ミルカとニクスが行動を共にすることとなった、ナノクニの事件で出会った狸獣人の少女だ。
くだんの事件で、ニクスはあかりと出会い、そして親交を深めるという言葉以上に仲良くなっていることをミルカも知っている。
紆余曲折があり、事件解決後、あかりと、その事件の中心にあった狐獣人の少女「こはく」はヴィーダの魔法学校に入学することになった。ミルカはもちろん、カイとも仲のいいクラスメイトだ。もちろん、あかりからニクスの話もよく聞いている。
詳細は相川GMの「白き姫巫女の受難」を参照のこと。
「あかりは元気か?……こはくも」
「こはくのついで感」
「い、いやそんなことは」
「元気にやってるわよ。毎日楽しく勉強してるわ。ニクスにも会いたいって言ってたわよ?」
「そうか……」
少しくすぐったそうに微笑むニクス。
で、と、ミルカは彼の後ろの金細工露店に目をやった。
「何見てたの?アクセサリー?」
「あ、ああ、金細工だそうだ」
なんとなくどぎまぎしてそちらに目をやるニクス。
それに便乗するように、露店の店主がにこやかに声をかけた。
「お嬢さんもどう?可愛いアクセサリーもあるよ!」
「金かー、きれいだけどちょっと貧乏学生には手が出ないかなー。あっ、でもそこそこお金持ちの友達ならいるから、お店の宣伝しておくわね!」
「そりゃーありがたい。じゃあ、この兄さんのアクセサリー選びも手伝ってやってくれよ」
「あっおい」
再度慌てるニクス。
ミルカはまたにこりと微笑みかけた。
「あかりは桃が好きらしいわよ」
「うぇっ?!」
ぎょっとするニクスに、にこにこしながらさらに続けるミルカ。
「今ね、お祭りだからみんなであちこち回ってるの。あかりとこはくも別のところ回ってるけど、後で合流する予定なのよね」
「ほ、ほう…?」
「…ニクスは?」
「…もう少しこのあたりを見て回ったら、少し休憩しようかと思ってたところだが…」
「ご休憩」
「ごは余計だ」
「喫茶店とかで?」
「ああ…そういえば、前にうまいハーブティーを入れてくれたところがあったな…確か、ハーフムーン、だったかな」
「ハーフムーンね。カイ、知ってる?」
「ああ、オルーカと行ったことあるよ」
「オルーカとも知り合いなのか?」
驚いた様子で言うニクスに、カイはあっさりと頷いた。
「うん、オルーカも学校のイベントごとに参加したことがあってさ。それで」
「なるほどな…」
納得したところで、ミルカはしゅたっと元気よく右手を上げた。
「じゃあ、あとでハーフムーンでね!」
「待て、どうしてそうなった」
「えっ、あかりを連れてきてほしくない?」
「連れてきてほしいですすみません」
意外に素直に謝ったニクスを微笑ましげに見てから、ミルカは改めてニクスに手を振った。
「あとで絶対、あかりとこはくを連れてくるからね!またねー!」
「ああ、またな」
手を振り返すニクスに背を向け、ミルカはうきうきとした様子で友人との待ち合わせ場所に急ぐのだった。
邂逅
「ええっ、ニクスに会っただか?!」
中央広場。
別行動をしていたあかりたちと合流したミルカは、早速ニクスとの約束をあかりに伝えた。
「ええ。あとでハーフムーンっていう喫茶店で合流しましょ、って約束したの」
「はーふむーん?」
「サザミ・ストリートにある小さなカフェだよ。あたしが場所知ってるから案内するよ」
カイが言うと、あかりは嬉しそうに微笑んだ。
「ありがとうだ!……あっ、でも……」
そこで、急に困ったように眉を寄せる。
「おら、これから姫ちゃんとぱんけーき食べに行く約束だっただ……」
姫ちゃん、とは、あかりと共にナノクニからやってきて魔法学校に入学した狐少女のこはくのことだ。先ほどまでミルカたちとは別ルートでバザールを回ってきていて、今はあかりの隣で話を聞いている。
あかりはオロオロと、ミルカとこはくを交互に見やった。
「姫ちゃん…」
「何を迷うことがあるのじゃ、ニクスに会いに行くといいのじゃ」
こはくはあっさりとそう言って、にこりと微笑んだ。
「姫もぱんけーきもいつでもあるのじゃ。しかし、ニクスはいつでもいるわけではない。あかりが会いたいと思うときに会えることはしあわせだと思うのじゃ」
「姫ちゃん」
「そうよーあかりちゃん。こはくちゃんとパンケーキには、パスティたちが行ってあげるからぁ」
「ふふっ、パスティはただパンケーキが食べたいだけでしょう…?」
こはくの後ろに立っていた白黒翼人の双子が笑顔で同意する。
友人たちの暖かな励ましに、あかりは少し涙ぐんで頷いた。
「あ……ありがとな、姫ちゃん、みんなも」
「よいのじゃ、よいのじゃ。その代わり、ニクスとどんな逢瀬じゃったかは報告するのじゃぞ?」
「あっ、パスティも聞きたーい!」
「あたしも興味あるわ…?帰ってきたら是非聞かせてもらわなくちゃ」
次々に言われ、あわあわと手を振るあかり。
「え、えええ?ほ、報告はその…恥ずかしいだよ…」
ミルカはその様子に苦笑して手を差し出した。
「まあまあ、それは後にして。ほら、ニクスも待ってるから、行くわよ」
「うう、後にしてってことはやっぱり聞かれるだな…」
「まあそれはもちろん」
「ううう…」
あかりは恥ずかしそうに、しかしミルカの手を取って歩き出す。
「わたしたちは別のところに用があるから、あかりをニクスに引き合わせたらすぐ行っちゃうけど」
「別のところ、だか?」
「うん、マルが来てるもんでさ。真昼の月亭で待ち合わせてるんだよ」
カイが言うと、パスティが楽しそうに手を合わせる。
「あらぁ、カイちゃんもデートなのねぇ?」
「デートかなあ?ミルカに会わせたことなかったから、いい機会だしと思って」
「うふふ、楽しみー」
ミルカは楽しそうに肩を揺らしてから、あかりの手を引いて歩きだした。
「じゃ、行ってくるわねー」
「行ってくるだ!」
「がんばるのじゃ、あかり!」
「がーんばってねぇー」
「今夜は帰ってこなくてもいいからねぇ?」
「いやいや、普通に門限守んなさいよ」
友人たちの無責任な声援に手を振り返し、あかりはミルカとカイと共に、喫茶ハーフムーンへと向かうのだった。
「あそこだよ、あの角の小さな店」
サザミ・ストリート。
大通りほどの喧騒はないが、この通りも継承祭を受けて各店舗が通りに出店などを出し、そこそこにぎわっている。
先頭を歩くカイが向こうの店舗を指さすと、ミルカとあかりは興味深げにそちらを見やった。
「へー、結構メルヘンチックな外観ね」
「可愛い店だだな」
「そうだね、前はちょっと怪しい薬屋だったみたいだけど…」
「この通り沿いに怪しい薬屋はちょっとそぐわないかもね…」
「ニクス、もう来てるだか?」
「うーん、会ってから結構時間たってるし、寄り道するにしてももう来てそうな気はするけど…」
と、首をひねったちょうどその瞬間。
どんがらがっしゃーん!!
まさに今向かおうとしていたハーフムーンからものすごい破砕音が聞こえ、3人は思わず足を止めた。
「な……なに?」
「店の中から聞こえた気がしたけど…」
「ちょっと行ってみよ!」
「あ、ちょっとカイ!」
躊躇なく駆け出すカイに、慌ててついていくミルカ。
カイは速足で入り口にたどり着くと、これまた躊躇なく開けた。
からん。
「今なんかものすごい音がしたけど、何?」
ひょいと中を覗いたカイの後ろからミルカも中を覗き込み、そしてぎょっとした。
店の奥にあるカウンターが半壊しており、その奥の戸棚に置かれていたであろう食器もろとも粉々に砕けてあたりに飛び散っている。
「えっ、どうしたの、強盗?!」
素っ頓狂な声を上げたミルカに、半壊したカウンターのあたりに立っていたニクスが慌てて手を振る。
「いや違うんだ、これは」
「え、ニクスが強盗?!」
「だから違う!これはその……」
「えっ、ニクスがいるだか?!」
ミルカのさらに後ろから、あかりがひょいと顔を出した。
「あかり?!また最悪のタイミングで…!」
さらにテンパるニクス。
まさか強盗ではなかろうが、状況がさっぱりわからない。あかりも何が何だかわからずにおろおろとあたりを見回すばかりで。
すると。
「はい、そこまで!」
ぱん!
大きな音を立てて手を叩いたカウンターの女性に一同の視線が集まった。
「え、ミリー先生?!」
「校長先生!」
「校長先生もおっただか!」
驚いてそちらを向く3人。
ミリーは立ち上がるとニクスの方を向いた。
「あなた。ここはもういいからお代払って出なさい」
「えっ。いや、しかし」
「いいから。この惨状は、ある意味ここの店主の自業自得よ。あなたに罪がないとは言わないけど、この人たちの罪の方が30倍重いわ」
「そんなに?」
ミルカがけげんな表情で問うも、ミリーが気にかける様子はない。
「飲食の正当な報酬だけ払って、犬にかまれたとでも思ってもう行きなさい。ほら、うちの生徒が待ち人なんでしょ?」
「いや、しかし…マスター」
気まずそうにカウンターの奥を向くニクス。
視線の先にいた、この店の店主と思われるギャルソンエプロンの男性は、苦笑して頷いた。
「ははっ、ミリーちゃんの言う通りだよ。お客さん、気にしないでカノジョとデート行ってきな?」
「そ……そうか?じゃあ…ごちそうさま」
なおもばつが悪そうに、しかしきっちりと代金を払ってから、ニクスは入り口に立つあかりのもとへ歩いていく。
「あかり!」
「ニクス!」
待ちきれないとばかりにニクスに駆け寄るあかり。
「久しぶりだな」
「うん!おら、ずっとニクスに会いたかっただ!」
「ああ、オレもだ」
あかりの頭をひとつ撫でてから、ニクスはミルカの方を見た。
「ありがとな」
「どういたしまして。いってらっしゃい、あかり」
「うん、行ってくるだ!」
「門限までには帰ってくるんだよー」
「わかっただー!姫ちゃんによろしくな!」
「はーい」
笑顔でニクスとあかりを見送り、カイとミルカは改めて店内の惨状を見やる。
「えっと……」
「で、なんなんですか、これ」
「言ったでしょう?この人たちの自業自得よ」
状況を把握できずに問うミルカたちに、先ほどと同じよくわからない答えを返して。
ミリーは半眼で、カウンターの中のマスターと、その隣にいた執事のような恰好をした男性を見やる。
「こういう痛い目を見たりもするんだから、ほどほどにしときなさいよ?」
「はぁーい」
「いえまあ、しかし、なかなかの珍味でございました。正統派の悪夢もたまには悪くありませんね」
「反省してないわね…」
妙に嬉しそうな執事に頭を抱えるミリー。
ミルカとカイはよくわからない様子で肩をすくめ、お互いを見る。
と、そこに顔を上げたミリーが声をかけた。
「ミルカちゃん」
「あっ、はい」
「悪いけどこれ、片付けるお手伝いをしてくれる?」
「えええ?!」
ザ・とばっちりである。
「わたし関係なくないですか?!」
「そうねえ、でもこの後あたし野暮用があってもう行かなくちゃいけないのよ。ここで会ったのも何かの縁と思って、手伝ってあげなさい」
「えー……」
「それか、あたしの代わりに野暮用こなす?最終的に東方大陸に行くことになるかもしれないけど」
「やらせていただきます」
恭しく礼をすると、ミリーは満足げに微笑んで踵を返した。
「じゃあ、あたしはこれで。お代はそこに置いておいたから」
「はーい、まいどありー」
出ていくミリーにあっさり手を振るマスター。
ミルカは不思議そうにそちらを見た。
「…ミリー先生、ここの常連さんなんですか?」
「あーうん、まあね」
マスターは歯切れの悪い調子で、それでも頷き返す。
ミルカはふうん、と不思議そうにそちらを見て、それからカウンターの惨状に目をやった。
「しかし、すごいことになってるわね…とりあえず大きなものから片付ければいいです?」
驚いてミルカの方を見るマスター。
「え、別にミリーちゃんの言うことは真に受けなくていいからね?」
「え?やりますよ?」
「いや、この後時間とか大丈夫?用事とかあるんじゃない?」
「そこまで急いでる用事じゃないから、掃除ぐらいできるよ」
カイが言い、ミルカも頷く。
「片付けるの大変でしょ?」
「うーんまあそうだけど、ミリーちゃんの言う通り、僕らの自業自得なところあるからねえ」
「僕ら、というか、主に私のですね」
何故か嬉しそうに、執事。
ミルカは肩を竦めて言った。
「まあ、経緯は何だったとしても、ミリー先生が片付けろって言うからには何かの意味があるんだろうと思うし、確かに大変そうだとは思うから。手伝いますよ?」
意外そうに眉を上げるマスター。
「…ずいぶんミリーちゃんのこと信頼してるんだね?」
「信頼って言うか…」
上手い言葉が見つからない、というように、ミルカは眉をひそめた。
「んー、ミリー先生は確かに横暴だし、唐突かつ強引で何考えてるかわからない割に逆らえない圧があるけど」
「言うねえ」
「でも、意味がないことは言わないしさせない人だと思うから」
「……」
にこり。
マスターは綺麗な笑みを浮かべてから、改めて店内の惨状を見渡した。
「じゃあ、手伝ってもらっちゃおうかな。大きなのは僕たちが片付けるから、動きやすいように椅子とか、周りのものとかよけてくれる?」
「わかりましたー。カイ、やろう」
「はいよー」
マスターの指示を受け、てきぱきとあたりを片付け始めるミルカとカイ。
マスターと執事は被害の中心となっているカウンター周りの瓦礫や木くずなどを片付けている。
椅子をどけ、被害から免れたカップや皿などを対比すべく、テーブル席の方まで持っていくと、ふと、出窓のところに置かれたフィギュアが目に留まった。
「…ん、これ……?」
なんとなく気になって目をやっただけだったが、すぐに目を見開いて至近距離でガン見の態勢に入る。
「これ……マミーランド・オオイタのクランシェシェ?!」
包帯から紫色の乾燥肌がなまめかしく覗く美少女7人のフィギュアを正確に言い当て、信じられない様子でさらに続ける。
「ていうかこれって……先月のイベントのえすたる亭の新作じゃ…?!」
言ってから、真相を正すべくマスターの方を振り返ると。
「こんなところでよろしいですかね」
「そだねー、じゃあとりあえずカウンターだけ直しちゃおっか」
ふわり。
マスターが手をかざすと、半壊していたカウンターは瞬く間にその姿を再構成し、壊れていたことなど全く感じさせない新品同様の姿に変貌する。
「!」
「わっ…すご」
ミルカの横でそれを見ていたカイも驚いて手を止める。
「あれって…変形術?にしてもすごすぎない…?あんなでかいものをあんな一瞬で…うちの先生だってもうちょっとかかるのに」
「……!」
ピンときた、という様子で、ミルカはマスターの方にずんずんと歩いていった。
「あ、ミルカちゃん、こっち出来たからとりあえず持ってってくれたもの戻し……って、えええ?」
ずい。
急にどアップで迫ってきたミルカに驚いて、彼女が身を乗り出した分だけ身を引くマスター。
ミルカはその整った容貌をじーっと見てから、おそるおそる言った。
「……もしかして……かるろさん……?」
マスターの目が一瞬だけ大きく見開かれる。
しかし、すぐにへらっと笑って、ひらひらと手を振った。
「あは、バレちゃったー?」
ミルカは目をさらに大きく見開いて声を上げる。
「えええ、本当にかるろさん?!」
「みるくさんが自分で言ったんじゃーん、まさか当てられるとは思わなかったなー」
「え、ちょ、本当に?!こんなところで、喫茶店の、えええ?!」
完全に混乱している様子のミルカに、マスターは楽しそうに笑い返した。
「みるくさんが入ってきたときはびっくりしちゃったし、ミリーちゃんの知り合いだってのもびっくりしちゃったよー。そういえば魔法学校通ってるって言ってたよね」
「あのショタ、本当に変形術で変身してたのね…かるろさんの新作があって、すごい変形術使うから、まさかと思ったけど…」
呆然とした様子で言うミルカに、カイが言いにくそうに声をかける。
「……よくわかんないけど、知り合い?」
「うん、そう。ていうかカイも見たことあるわよ。ラージサイト・ヴィーダで」
「うわ、そっち方面の知り合いなんだ」
「よくうちのスペース遊びに来るじゃない、えすたる亭のかるろさん」
「え……あ、あのちっちゃい子?!マジで?!」
やはり驚いた様子のカイ。
「……よくわかりませんが、皆さんお知り合いということですか?」
マスターの傍らで執事が不思議そうに首をかしげると、マスターが苦笑してそちらを向いた。
「ちょっと、趣味関連でね。僕はこの姿じゃないから、混乱させちゃうと思って言わなかったけど、まさか当てられちゃうなんてさー。みるくさんはカンがいいんだね」
みるく、とは、くだんの趣味関連のイベントでのミルカのペンネーム。
そして、かるろ、というのも、そのイベントでのマスターのペンネームだ。加えて、マスターはそのイベントではどうやら得意の変形術で少年の姿になって参加しているらしい。カイはそちら方面にはまったくもって疎いのだが、よくミルカの手伝いでイベントに駆り出されているため、その少年の姿は目撃したことがあった。
「まー、僕は普段はここでマスターやってるからさ、ここではかるろじゃなくて、マスターって呼んでよ。ね、ミルカちゃん?」
マスターがそう言って微笑むと、ミルカは息をついて頷いた。
「わかったわ、プライベートとヲタ活はきっちり線引きしなきゃね」
それから、にこりと微笑んで手を差し出す。
「改めて、ミルカ・アレディーナよ。よろしくね」
マスターも微笑んでその手を握り返した。
「よろしく。僕のことはマスターって呼んでね。ミルカちゃんならサービスしちゃうよ」
「ええ、このお店のお茶もケーキも美味しいってカイが言ってたから、わたしも通わせてもらうわね」
「嬉しいなー、常連さんゲット!」
ふふふ、と微笑みあい、和やかな空気が流れたところで。
「んじゃ、あたしは向こうから食器戻すから、あんたは残りのガラス片とか掃いちゃってよ」
カイが箒とちりとりをミルカに渡した。
「はぁーい」
テンションが上がっていたところで急に現実に引き戻され、ミルカは面倒げにガラス片を掃き始めた。
からん。
「こんにちはー………って、あれ?」
来客を告げるドアベルの音にも構わず、文句をたれながら集めたガラス片をちりとりに掃き入れていく。
「もー、なんでわたしが片付けなきゃいけないのよー」
「まあまあ、あと少しだから、ほら」
カイが食器を運びつつ励ましていると。
「あっ…カイさん、ミルカさん!」
唐突に名を呼ばれ、ミルカとカイはそちら…入口の方を振り返った。
「あれ、オルーカ!」
「オルーカじゃん、久しぶり」
そちらには、二人の友人であるオルーカの姿があった。
手早くちりとりのゴミをゴミ箱に捨てたところに、オルーカが嬉しそうに駆け寄ってくる。
「お久しぶりです」
「ホントに久しぶり!元気だった?」
「ええ、おかげさまで。ええと、開店準備中…でしたか?」
「え?あ、ううん、ちょっと散らかっちゃったからお手伝いしてたの。わたしは店員じゃないし」
はい、と執事に箒とちりとりを返し、ミルカはオルーカに向き直った。
「そうなんですね。お疲れ様です」
オルーカは安心した様子でミルカに言い、隣でやはりぞうきんを執事に返していたカイの方を向く。
「カイさんもお元気でしたか?その後お変わりはありませんか?」
「うん、ぼちぼち元気だよ。変わったことと言えば……」
「婚約したことくらいよね」
「ああ、そうだね」
「ちょっ、婚約?!何ですかそれ詳しく!!」
前のめりで聞くオルーカに、カイは苦笑した。
「この後その相手と待ち合わせてるんだけどさ。紹介できればいいけど……いいの?連れがいるんでしょ?」
「……はっ!そうでした……」
思い出したくないことを思い出してしまった、という様子で、オルーカは後ろを振り向く。
そこには。
「ほうほう、これはマミーランド・オオイタのクランシェシェではないですか~!ふふふ揃え方、並べ方にもこだわりを感じますなぁ~!
まったく、こんなにいい喫茶店を知っていながら、どうしてもっと早く知らせなかったのでしょうね!オルーカは!ガルダス神の怒りに触れますよ!」
出窓に並べられたフィギュアを嘗め回すように見つめながら、デュフデュフと不気味な笑い声をあげている不審人物がいた。
「……なんかどこかで見たことあるような気がするし、あんまり聞きたくないけど…オルーカの……えっと、知り合い?」
若干嫌そうな顔でミルカが問うと、オルーカは言いづらそうに不審者を手で示した。
「し、紹介するのもイヤなのですが、うちの僧院の司祭なんです…お話があると言われて、ゆっくり話せるここに案内したんですが…うう、やっぱりやめておけばよかった……」
血の涙を流しかねない勢いで言うオルーカに、ミルカは同情した様子で肩に手を置く。
「わかるわ……大変な上司を持つと大変よね…大体みんな同じような目に遭ってるのね……ミケとか千秋とか」
「千秋さんはラブラブだからいいじゃないですか……うう…というわけですみませんお二人とも。また今度ゆっくりと!」
一瞬で元気を取り戻したオルーカは、二人にしゅたっと挨拶をした。
「あ、う、うん」
「またねーオルーカ。じゃ、わたしたちも行きましょうか、カイ」
時計を見てみれば、マルとの待ち合わせ時間が迫っている。カイを促すと、彼女も頷いた。
「そうだね」
「またお話聞かせてくださいね。特に婚約者とか婚約者とか婚約者とかを!」
「はいはい」
苦笑して手を振り、ミルカとカイはハーフムーンを後にした。
「そういえば、何も言わなかったね」
「え?」
ハーフムーンから真昼の月亭への道すがら、唐突に言ってきたカイに、ミルカは発言の意図を図りかねて首をかしげる。
カイは視線だけをそちらによこして、続けた。
「ミリー先生。何も言ってこなかったよね」
「何も、って?」
「あんたもう忘れたの?フィズと会えなくなるかもしれないって半泣きで心配してたのに」
「あっ」
あまりに斜め上からいろんなトラブルが降り注いだためすっかり忘れていたが、確かにミリーはミルカに対して何も言ってこなかった。掃除を断りかけた時に東方大陸がどうのと言っていたが、これも掃除をやらせるための脅しに過ぎない。その掃除も、おそらくはマスター=かるろと引き合わせるための計らいだということは薄々感じていた。
「…確かに、フィズのことは何も言ってこなかったわ。用事も言いつけられてないし」
「じゃあ、もう継承祭の間は安心していいってことじゃない?」
「そうかなあ」
「そうそう。がんばってたミルカへのご褒美ってことで」
「…そうね!」
まだ不安はあったが、そうして励まそうとしてくれているカイの気持ちを無にしないためにも、ミルカは努めて明るく頷いた。
「そうと決まれば、継承祭楽しんじゃいましょ!カイは、そのマルくんとはどこか回る約束してるの?」
「んーと、今日はちょっとしか時間取れないって言ってた。なんか、親戚関係のあいさつ回りとかがあるんだって」
「へー…竜族の中でもそういうの結構厳しいのね」
「あいつ意外とボンボンなんだよね」
「…そのボンボンとお見合いしたカイも結構いいところのお嬢様なんじゃ…?」
「ははっ、まあ狭い世界だからね、土地によっていろいろだよ」
「あっ、ごまかした」
「はいはい、到着ー。さ、行こう」
そんなことを言っている間に真昼の月亭に到着した二人は、からん、とドアベルを鳴らして中に入っていった。
「え、えっとぉ…マーロウ・スタインですぅ……マルって呼んでくださいぃ…」
真昼の月亭で正面に座った少年は、びくびくおどおどした様子で頭を下げた。
背丈を半分くらいにしているのではと思うほどの猫背、赤いたれ目とそばかすを大きな眼鏡で隠し、無造作な赤毛を前髪だけまとめて縛っている。
「…………」
ミルカはたっぷり10秒ほど彼を見つめ、それからカイの方を向いた。
「……政略結婚?」
「あんたも大概失礼だね」
「うそうそ。わたしはミルカ・アレディーナよ。カイのルームメイトなの。ミルカでいいわ。よろしくね」
気を取り直してにこやかに挨拶すると、マルと名乗った少年もへらっと笑って握手を返す。
ミルカは改めてしげしげとマルを眺めた。
「でも、まあ、ちょっと意外だったわよ。みんなそう言わない?」
「まあ、気持ちはわかるよ。こいついつもこんな感じだしね」
「え、えへへ…すみません……」
眉尻を下げて謝る姿は見るからに気弱で、隣にいる快活な少女の婚約者とはとても思えない。
「何が良かったの?いや、お互いにさ。なんかあまりにもタイプが違いすぎて」
「か、カイさんは素敵な方ですよぉ!僕、一目惚れだったんですぅ!」
思いのほかマルが食いついてきて、ミルカはその勢いに思わず後ろに身を引いた。
「そ、そうなのね」
「カイさんはぁ、太陽のような人なんですぅ!明るくて快活で、強くてまっすぐでぇ、僕の行く先を照らしてくれるような、僕の女神なんですぅ!」
「ロープロープ。わかったから」
さらに身を乗り出してくるマルをどうにか抑えてから、苦笑してカイの方を見るミルカ。
「またずいぶん好かれたものね。乙女ゲーの口説き文句みたい」
「ははは、まあこういうやつなんだよ」
「そうなると、カイがなんでこの人を気に入ったのかがよくわかんないなー。これだけ褒めてくれるのは、友人として普通に嬉しいけど」
「悪い奴じゃないよ?」
「悪い人じゃないのはわかりすぎるほどわかるけど」
「あとねえ」
カイはかなり上機嫌で、ぴっとマルを指さした。
「こいつ、こんななりしてめっちゃ強いんだ」
「あ、把握したわ」
一瞬ですべてを理解したミルカは、あらためてしげしげとマルを見やった。
「なるほど…人は見かけによらない…このビジュアルでカイより強かったらそりゃ盛大なギャップ萌えだわ…
NLでもカイマルで決まりかと思ってたけどワンコ下克上のマルカイもワンチャンありかも……?」
ぶつぶつとつぶやきだすミルカを、今度はマルがびくびくした様子で見る。
「あ、あのぅ……大丈夫ですか…?ミルカさん…」
「ああ、まあ持病みたいなもんだから気にしないで」
親友の婚約者との邂逅の時間は、穏やかにゆっくりと過ぎていった。
別離
「で、今日はどうすんの?」
翌日の昼下がり。
出かける支度をしながら、何気ない様子そう訊ねるカイに、ミルカはうーんと考えた。
「んー…昨日ちょっとしか見れてないから、バザール回ろうかなと思ってたんだけど。カイは?マルとデートでしょ?」
「そうだね、あたしらもバザール回って…夕方に中央公園のメインステージで魔法の演武があるっていうからさ、見に行こうと思ってたんだよ。あんたも一緒にどう?」
「いやーさすがに若いカップルのお邪魔を何日もできませんわー。二人で楽しんできて?」
冗談めかして年寄りの口真似をしてからひらひらと手を振るミルカに、苦笑するカイ。
「わかった、そうするよ。まあでも、バザールまでは一緒に行こうよ。マルももう下で待ってるだろうからさ」
「そうなのね。じゃあそうしようかな」
リボンをきゅっと結び終えたミルカは、先に部屋を出たカイの後に続いて部屋を出た。
「あっ、カイさぁん!」
「お待たせ。ごめんね」
寮の出口で待っていたマルは、カイの姿を見て嬉しそうに駆け寄ってきた。やっぱりワンコのようだなと思うミルカ。
「じゃ、行こうか」
「はーい」
マルと合流し、カイが先頭を歩き出して校門へと向かう。
すると、休日だというのにそこに誰かが立っているのが見えた。
長い金髪をポニーテールにした女性のようだ。魔法学校では見かけない姿である。
すると、カイが何かに気づいた様子で声を上げた。
「あれっ、レティシアじゃない?」
思わぬところから名を呼ばれた、という様子で、長いポニーテールがくるりと振り返る。
そして、カイの姿を認めるとぱっと表情を広げた。
「カイ!久しぶりね!」
カイが歩いていくのを待てないというように駆け寄ってくる少女。
カイは気さくに彼女に話しかけた。
「久しぶり。学校に何か用だった?」
「え、と、うん、まあ。もう用は終わったから帰るところよ」
何かをごまかすように言ってから、ミルカに視線を向けて。
「ところでカイ、こちらのカワイイお嬢さんはお友達?今日はマルは?一緒じゃないの?」」
「ここにいますぅ……」
弱々しい声とともに、カイの後ろからひょいと顔を覗かせるマル。
少女はあはは、と笑った。
「ごめんごめん、気づかなくて……それで、こちらの方は?」
「こっちはミルカだよ。あたしのルームメイト」
カイが紹介したので、ミルカは笑顔で挨拶をした。
「初めまして、ミルカ・アレディーナよ」
「ミルカね。よろしく。私は、レティシア・ルードよ」
「レティシア…なら、ティッシね!よろしくね!」
速攻で愛称をつけるミルカ。レティシアは特に気にした様子もなく、話を続ける。
「私の勘違いだったらゴメンね。私、ミルカとは初対面じゃないような気がするんだけど、どこかで会った事あったっけ?」
「ううん、初対面だと思うけど……うっ……わたしの頭に何かの電波が…ブルーポスト……黒ボンデージ……ううっ、頭が!」
「ちょっ、なんか私の頭にも来そうだけど大丈夫?!」
「大丈夫大丈夫。まあほら、最初から波長が合って自然体で話せる相手っているわよね!」
「そ、そうよね…?」
不思議なやり取りをしているところに、カイが横から尋ねる。
「そういえば用事って?」
「ああ、それがね……マヒンダにある実家に帰る事になったから、知り合いに挨拶に来たの」
「えっ、レティシア帰るの?」
驚いた様子で、カイ。
「そうなの。ちょっと、家の事情でね」
苦笑するレティシア。どうもそれ以上のことをあまり言いたくない様子で。
「3人はこれからどこかに行くの?」
「バザールの方に行こうと思ってたんだ。レティシアは?」
「あ……じゃあ、ご一緒していい?そっちの方に行こうと思ってたんだ」
やはりぎこちない様子で微笑むレティシア。
それには気づかないふりをして、4人はともにバザールに繰り出した。
「私が冒険者として一番最初に受けた依頼が、実はカイの依頼だったのよね」
歩きながら、懐かしそうに言うレティシア。
カイは意外そうに眉を上げた。
「そうなんだ?懐かしいね」
「そうだね…ロッテの事件で会ったり、パフィの事件で会ったり……マルの依頼に関わったりもしたわね」
「そ、そのせつはお世話になりましたぁ……」
ぴく、と耳が動いて身を乗り出すミルカ。
「えっ、じゃあ、マルカイのキューピッドをティッシたちがやったってこと?」
「そうなの。まあ私はあんまり何の役にも立ってなかったけど…」
「そ、そんなことないですよぉ……あのぉ、皆さんには本当にお世話になってぇ……」
しみじみと言うマルに、今度はレティシアが興味津々な様子で訊ねた。
「その後、カイとはどうなの?進展してる?」
「し、ししし、進展ですかぁ?」
真っ赤になって慌てるマル。
あ、こりゃあんまり進んでないな、という顔をするミルカとレティシア。
ミルカはくすくす笑ってその話に乗った。
「マルがカイのところに来た話、なんか相当面白かったって聞いたから、ちょっとその場に居合わせたかったわ」
「ミルカは、カイのルームメイトなのよね?」
そこにレティシアが聞いてきて、素直にうなずく。
「そうよ」
「サバサバしたカイと、なんていうか、対照的っていうか……その服とか」
「ああ、これ?都会の魔道士学校に入学するって言ったら母が作ってくれたんだけど…田舎者の発想は何かズレてるのよねー」
苦笑して言うミルカに、レティシアはとんでもないというように手を振った。
「そんなことないわよ!すっごく似合ってる!髪の毛も…それ、どうしてるの?」
「地毛なのよー。ちょっと油断すると爆発しちゃうの。ティッシみたいなさらさらストレートがうらやましいわ」
「長いと大変よねー。おすすめのヘアケアとかある?」
「最近のお気に入りはね、スイートエンジェルっていうブランドの……」
乙女のファッション談義はバザールに到着するまで続いた。
バザールの入り口に到着すると、レティシアは3人を振り返った。
「カイたちはどっちへ行くの?」
「そうだね、あんまり決めてないけど……昨日通りがかった時に、なんかよさそうな武器売ってるところがあったから、そっちに行こうかなと思って」
そっち、と言って目的の方向を指さすカイ。
レティシアは笑顔で頷いた。
「そうなんだ。じゃあ私は反対方向だから、ここでお別れね」
残念そうな、しかしどこかぎこちない様子で言うレティシアを、ミルカは黙って見つめていた。
「また会えたら会いましょう。カイ、マル、元気でね。マヒンダに来る事があったら『蒼月の館』って食堂に来て。私の実家なの」
「蒼月の館、ね。覚えとく」
「あ、あのぉ、レティシアさんもぉ、お元気で……」
カイとマルの挨拶が終わり、レティシアは改めてミルカの方を見る。
「初めましてなのに、ちっとも初めてな感じがしなかったわ」
「ふふ、わたしも」
「やっぱりどこかで会ってたのかもね」
「本当に。せっかく知り合えたのにもうお別れだなんて寂しいわね」
「そうね……ミルカもマヒンダに来たら、ぜひ実家に遊びに来て」
「ええ、必ず!」
おそらくは、彼女はいつもこんな風に快活な人柄なのだろう。しかしどこかぎこちなく見えるのは、わずかに赤い目元のせいだろうか。
触れられたくない様子のそれには特に触れることなく、ミルカは出会ってすぐの別れを惜しんで手を振った。
「しっかし賑やかねー…」
武器屋を見て回るというカイたちと別れを告げ、ミルカは再びバザールを歩き回っていた。
ヴィーダの祭り成分をすべて凝縮したこの一週間は、国内外から多くの人々が集まっている。冗談抜きでいつもの倍はいそうな人出だ。
「知り合いとすれ違ってもわからなそうだわ……ん?」
呟いたところで、さっそく見知った顔を見つけるミルカ。
パッと顔を輝かせ、駆け寄って声をかける。
「クローネ!久しぶり」
彼女が声をかけると、背の高い男性……クローネはきょとんとした様子で振り返った。
それから、にこりと綺麗な笑みを浮かべる。
「ミルカちゃん。久しぶり、元気そうだね」
「おかげさまで。クローネも元気そうね。お仕事?」
「んーまあ、仕事というかなんというか。今このタイミングはどっちかって言うとプライベートかな」
「プライベートで、可愛い子ちゃんとデート?さすがイケメンはやることが違うねぇ」
オヤジくさい感想を述べながら、クローネが連れている女性に目をやる。改めて見てみれば、目が覚めるほどの美女だ。線が細くはかなげで、身に纏っているものもふわふわと可愛らしい。一見ミルカの服と似ているようで、しかし確かな品の良さを感じる服だ。
女性はにこりと微笑むと、ミルカに言った。
「クローネ兄様の、おともだちのかたですか?」
「兄様?」
驚いて二人の顔を見比べる。美形はそれだけで至宝なのであまり意識しなかったが、確かに二人の顔立ちはよく似ていた。
「え、妹さんなの?うっそ、可愛い!」
妹を褒められてか、上機嫌でクローネは横の女性を紹介した。
「俺の妹、ノーラだよ。ノーラ、こちらはミルカちゃん。前に仕事でかかわったことがあるんだ」
「そうなのですね。ノーレイン・デ=ピースと申します。兄がお世話になりました」
丁寧に頭を下げるノーラに、ミルカは慌てて手を振った。
「いえいえこちらこそ!クローネにはすっかりお世話になっちゃって。ミルカ・アレディーナです。よろしくね」
「ミルカさん、ですね。よろしくお願いいたします」
「ノーラって呼んでいい?」
「もちろんです」
ノーラはふふっと笑って、ミルカの身に纏っている服をしげしげと見つめた。
「ミルカさんもお可愛らしいけれど、このお衣装もとっても素敵です。どちらでお求めになったの?」
「これ?恥ずかしながら、母親が作ってくれたのよ」
「まあ!これを、おかあさまが?!」
心底驚いた様子のノーラ。
「すごい……ミルカさんのおかあさまは、お裁縫がお上手なうえに、とってもセンスが良くていらっしゃるのね…!」
キラキラと目を輝かせてミルカの服を見つめるノーラ。
逆にそんな彼女が眩しくて、ミルカはクローネに素直な感想を告げた。
「…天使かな?」
「でしょ」
全力で肯定する兄馬鹿のクローネ。
ミルカはため息交じりに、改めて二人の顔を見比べた。
「はぁ~……血筋って素晴らしいわね…あとはミケだっけ?」
ブルーポストのイベントで少しだけすれ違った、クローネの弟のことを思い浮かべる。彼もまたなかなかの美丈夫だった。
「ノーラはミケの……」
「姉です。ミケもお世話になっているのね」
「ひゃー美形兄弟……」
「もう一人、俺の上にグレシャムっていう兄がいるんだよ」
「その人も美形?」
「それはもう」
もはや謙遜という言葉も意味を忘れかけるほどに全力肯定するクローネ。
ミルカはひとしきり美形を堪能すると、改めてノーラに話しかけた。
「今日はクローネとショッピングなの?」
「ショッピングというか、明日、家族で故郷に帰るまで少しお時間があるので、せっかくですからお祭りを見て回っているのです」
「え、もう明日帰っちゃうんだ」
クローネの、つまりノーラのでもある故郷は、フェアルーフ王国の北に位置するザフィルスだ。以前、お使いがてらの依頼でかかわったことがあるが、移動に魔道の力を借りたいほどにはそれなりに遠くである。
「っていうことは、ミケも一緒に帰るのね…ノーラとも、せっかく知り合えたのに残念」
本当に残念そうに言うミルカに、ノーラはふふっと微笑みかけた。
「では、もう少し私たちとお買い物をしませんか?せっかく出会ったのですもの、私ももう少し、ミルカさんと可愛らしいものを探したいわ」
相変わらずのきらきらとした微笑み。
ミルカはほわーっと目を細めて、それからもう一度クローネに言った。
「天使かな?」
「でしょ」
「この辺はファッションゾーンなのかな?服とかいっぱいあるね」
少し歩き回ると、あたりは華やかな服やアクセサリーが並ぶエリアになっていた。クローネがそう言いながら、物珍しげにあたりを見回している。
昨日ニクスに遭遇したのもこのあたりだったように思う。あの後すぐに寮に戻ってしまったので、あまりじっくり回っていなかったのだが。
「…ん、でも何で釜飯の匂いが…?」
ファッションのエリアにあまり似つかわしくない、食欲をそそる匂いに、きょろきょろとあたりを見回すミルカ。
すると、視線の先には妙にけばけばしい色の服がずらりと並べられた出店。よくわからないが釜飯の匂いはそこからしているようだ。
「……あれっ?」
鼻歌交じりに服の整理をしているのは、こちらもまた見知った顔だった。
「ンリルカじゃない?久しぶり!」
ミルカが声をかけると、グラマラスな白髪の女性はこちらに気づき、そして……女性のものとは到底思えない野太い声で嬉し気に体をくねらせた。
「あらぁ!ミルカちゃんじゃな~い!ひっさしぶりぃ、20年ぶりくらいかしらぁ?」
「久しぶりンリルカ、言ってもFirstAdventureぶりじゃない?近い近い」
ミルカがひらひらと手を振りながら歩み寄ると、ンリルカは嬉しそうに歓迎の姿勢を見せ、そしてミルカの後ろにいるクローネにも目ざとく視線を送る。
「はぁーいvクローネくん、相変わらず幸薄そうでキュンキュンしちゃうわ♪」
「あ、やっぱり俺のこと覚えてた?久しぶり、ンリルカちゃん」
苦笑して手を振り返すクローネ。
そもそもが、ミルカがンリルカと出会ったのが、クローネがかかわったザフィルスの事件なのだ。
そして、ンリルカはさらに、クローネの傍らにいたノーラにもねっとりと視線を向けた。
「でぇ、その後ろにいるカワイイカワイイオンナノコは誰かしらぁ?」
クローネが紹介するより先に、ミルカが彼女の横に立ち、きゅっと腕を引き寄せる。
「ノーラっていうの!クローネの妹さんで、だからミケのお姉さんになるわね!」
「ノーレイン=デ・ピースです。良しなにお願いいたします」
ノーラが丁寧にお辞儀をして言うと、ンリルカは嬉しそうに礼を返した。
「ノーラちゃんねぇ☆ンリェンは今は辛梨寺ンリェンよぉ、よろしくね♪」
「からり……」
「ンリルカちゃんでいいから。ね」
言われたことをそのまま繰り返すノーラに、クローネが苦笑して念を押す。
「ンリルカ、フリマでもやってるの?」
派手派手しいラインナップをしげしげと眺めながら言うと、ンリルカはふふふふと笑って頷いた。
「そうなのよぉ☆実はねぇ、勤めてたお店が潰れちゃってぇ、お店の衣装とかを売ってるわけ。
さっきまでイチオシの目玉商品が並んでたんだけどぉ、商売人のグレシャムくんが全部売ってくれてぇ」
「えっ、グレシャム兄貴も来たの?」
ぎょっとして問うクローネに、笑顔で頷くンリルカ。
「そうよぉ、ミケくんと仲良くランデブーだったわぁ?それにしても兄弟みんな美形とか眼福よねぇ~」
「そっか、兄貴たちもこの辺回ってるんだな…」
先ほど名前の出ていたグレシャムが、どんな経緯か全く不明だがンリルカの店で店番をしていたらしい。ちょっと見てみたいと思いつつも、とりあえず黙っておく。
ンリルカはさらに続けた。
「それでぇ、目玉商品はグレシャムくんが全部売っちゃったからぁ、今こんなのしか残ってなくてごめんなさ~い?」
じゃん。
口で効果音を出して、ンリルカは2枚の板を出した。
「薄幸そうなクローネくんには…
突然[全裸になった時に股間に当てる銀のトレイ]か、突然[全裸になった時に股間に当てる用の天狗のお面]を選択制でプレゼントしちゃうv好きな方を選んでね☆」
「いやいやちょっと待って?!ツッコミどころは一つにしてくれるかな?!なんで突然全裸になること前提なの?!」
慌ててツッコミを入れるクローネに、ミルカが同調するように言い募る。
「そうよンリルカ!クローネのご立派様がそんなもので隠れるわけないでしょ?せめて天狗の鼻2倍にしてくれないと!」
「ミルカちゃんも引っ掻き回さないでくれない?!」
「あらやだぁ、ンリェンとしたことが☆それじゃあそうねぇ、こっちのテングザルバージョンはどうかしらぁ?」
「大きさの問題じゃなくてね?!」
「クローネお兄様、全裸になられるの?」
「ノーラは聞かなくてよろしい、耳塞いでなさい」
楽しそうにクローネをいじるミルカとンリルカを、ノーラは不思議そうに見つめているのだった。
ンリルカの店を後にし、ミルカは変わらずクローネとノーラとバザールを回っていた。ンリルカの店では結局天狗のお面2個を押し付けられて終了だったので、ノーラの可愛らしい服を引き続き見て回っている。
「いや、俺はいらないんだけどねこのお面?」
「え、やっぱりテングザルでも隠れないの?」
「ミルカちゃんそろそろセクハラで訴えてもいいよね?」
などというのんきな会話を交わしていると。
「探したわ、ここにいたのね」
正面から声がしてそちらを向く。
そこには。
「…ミリー先生!」
「ミリー校長」
いつものように堂々とした足取りでこちらに歩いてくるミリーに、ミルカとクローネが同時に声を上げる。
クローネとかかわった事件は、もともとミリーがクローネとミルカを引き合わせたようなものだ。クローネはいつもの愛想よい笑みで、こちらにやってきたミリーに挨拶をする。
「ご無沙汰してます。お元気そうで何より」
「クローネと一緒だったのね。お久しぶり」
ミリーはクローネの挨拶に微笑みを返した。
「ザフィルス国王の警護はお兄様だったように記憶しているけど?」
「そんなことまで知ってるんですか…こわ」
「なにか?」
「いえ何も。俺は仕事半分、プライベート半分ですね。こちら、妹のノーレインです」
「ノーレイン・デ=ピースと申します。兄がお世話になっております」
ミルカと違ってそれなりに丁寧にあいさつをする兄に倣ってか、ノーラも恭しく礼をした。
「ミレニアム・シーヴァンよ。魔道学校の校長をしているの。よろしくね」
そちらにも鷹揚に笑みを返し、ミリーは改めてクローネに向き直った。
「悪いけど、ミルカちゃんを借りられるかしら」
「えっ、わたし?」
てっきりクローネに用があるものだと思っていたら、まさかの自分指名にきょとんとするミルカ。
クローネはにこりと笑みを返した。
「彼女さえよければ。もともと、俺たちとも偶然行き会ったようなものなので」
決定権をゆだねられ、ミルカは戸惑いつつも頷く。
「…わかりました。じゃあクローネ、ノーラ、わたしはここで。楽しかったわ」
「お別れは名残惜しいけれど、私も楽しかったです。ミルカさんも、ザフィルスにおいでの際はぜひお顔を出してくださいね?」
若干残念そうなノーラに笑みを返して、ミルカはクローネにも向き直った。
「クローネも元気で。ミケにもよろしくね。あと、美形のお兄さんにも」
「よろしくは伝えとくけど、ノーラの言う通り、いつか遊びに来てよ。歓迎するからさ。兄貴も紹介するし」
「それはぜひ。じゃあ、またね。ザフィルスまでの道中も気を付けて!」
陽気に手を振って、ミルカは二人に別れを告げた。
「で、わたしどこに連れていかれるんですか?」
「割とすぐそこよ。昨日までちょろちょろしてたんだけど、邪魔なのが捕り物騒ぎで連れてかれたからようやく居場所を掴めたの」
「……?」
ミリーが何を言っているのかよくわからないが、とりあえず彼女の後についていく。
彼女の言うことに逆らう気はさらさらないが、やっぱり、という様子で、ミルカはため息をついた。
「はぁ……割とすぐそこで何かがあった挙句に今度は東方大陸に飛ばされるのね……そんな気がしてたのよ、フィズが来てるのにミリー先生が何も言わないなんて不気味通り越して天変地異としか思えないんだから」
「ずいぶんな言いぐさねえ」
仕方ないというように苦笑するミリー。
ミルカは諦観という形容詞が似合う乾いた笑みを返した。
「いえ、なんというか、予定調和だなって思っただけです。今度は何のお使いですか?」
「ご期待に沿えなくて残念だけど、今回はお使いじゃないわよ」
ふ、と意味深な笑みを見せて、ミリーはゆっくりと告げた。
「……会わせたい人がいるの」
憧憬
その場所は、ファッションの区画からほど近く、どうもコスメや美容グッズが並んでいるエリアのようだった。
エリアの多くを占めているのが、最近流行の二大化粧品ブランドである。マジカルスティックと、スイートエンジェルだ。
「へぇ、スイートエンジェルも出してるのね…わ、継承祭限定とかある。あとでゆっくり見よう…!」
ミルカは先ほどレティシアにも勧めた通り、スイートエンジェルのコスメを好んで使っている。マジカルスティックは発色も良いし派手で綺麗だが、自分には合わないと思っていた。
「しかし、ライバルブランドを隣に並べるとか、なかなか思い切ったことするわね…」
マジカルスティックとスイートエンジェルはファンも店舗も誰もが認めるライバルブランドで、お互いに反目しあっていると聞く。店構えも白が基調のふわふわと可愛らしいスイートエンジェルに対し、黒をベースに派手な色が並ぶマジカルスティックはあらゆる意味で対照的な印象があるし、どちらが先行かはわからないが定員も客もお互いを意識しあっているように見えた。
「……会わせたい人がいるって、ここにですか?」
「ええ。さっき娘が出てきたから間違いないと思うわ」
「娘…?」
ミルカの疑問に答える気は無いようで、ミリーはさらにブースの奥へと足を進めていく。ミルカは小走りでそれについていった。
やがて、ブースの一番奥、会計のレジの隣にある基礎化粧品ブースにたどり着く。そこには、ディスプレイの細かい調整をする女性の後ろ姿があった。
ウェーブのかかった銀髪をリボンで止め、臙脂色のカットソーと灰色のロングスカート、厚手のショールというどこにでもいそうないでたち。綺麗に着飾っている店員の女性たちとも明らかに雰囲気が違うが、ディスプレイの調整をしているということは店の関係者であろうか。
彼女は後ろに誰かが立った気配を感じたのか、ゆっくりと振り返った。
と同時に、ミルカの瞳が大きく見開かれる。
忘れもしない。その顔。その姿。
幼いころに一度だけ。それでも、彼女の記憶に強烈に焼き付き、彼女の人生を鮮やかに変革した人物。
「……ミシェル……?!」
ミルカは驚き半分、喜び半分で慌てて彼女に駆け寄った。
「ミシェル……ミシェル、さん、ですよね?!」
半ばすがるようにして彼女のショールを掴み、必死に訴える。
「あのっ!覚えてませんか、10年くらい前に、魔物に襲われた村を助けてくれたこと…!」
彼女の表情は穏やかに微笑んでいるように見えたが、突然の訴えに驚きも戸惑いもしていないその様子は、ゆるい笑みの仮面を張り付けているようで、ぼんやりとした違和感があった。
すると。
「やっぱり、あなただったのね」
ミルカの様子を後ろで見ていたミリーの声がして振り返る。
彼女はこれまで見たこともないほど、ひどく満足げに微笑んでいた。
ふ、と笑みを深めてから、恭しくお辞儀をする。
「お久しゅうございます。ヒューリルア・ミシェラヴィル・シュタルト総評議長」
あらゆる意味で初めて見るミリーの姿に、ミルカは混乱した様子でそちらを見る。
「ミリー先生…?」
すると、ミルカの背後で、ふ、と浅い嘆息が聞こえた。
「……まさかこんなところであなたに会うとはね。ゲルソライト・ミレニアム・シーヴァン」
冷たささえ滲む声音に再びぎょっとして振り向く。
すると、女性……ミシェル、と呼んだその人物は、先ほどの穏やかな笑みからは想像もできない冷たい無表情でミリーの方を見やっていた。
(ど……どういう…こと?)
2人が知己の間柄であったこと。
それもどうやらミリーがミシェルを敬う立場であるらしいこと。
優しかったミシェルのひどく冷たいふるまい。
何もかもが想定外で、ミルカはただひたすら戸惑ったまま、二人の顔を交互に見やるのだった。
「ここなら声が外に漏れない対処をしているわ」
案内された家は、大通りから少しわき道にそれた先に広がっている、細く複雑な通路の先にあった。
ここで話すことではないから、と短く淡々と言われ、ミリーとミルカはミシェルについてきた。相変わらず無言のミシェルと、上機嫌のミリーを不安そうに見やる。
(まさか二人が知り合いだったなんて…ど、どういう関係なのかしら…)
あまりにもタイプの違う二人だからか、まったくもって想像もつかない。
ミルカは黙ったまま不安げに二人の顔を見た。
「……それで」
ゆっくりと、言葉を選ぶようにしてミシェルはミリーに言った。
「…私に、何の用かしら」
「ご挨拶ですね?久しぶりにお会いできたというのに」
何度聞いても、ミリーの口から紡がれる敬語に全く慣れない。それは、いつもと違うからという以上に、ミリーの態度そのものが不遜ともいえるほどに自信に満ち溢れているからだろう。
ミシェルもそれは感じ取ったらしく、少し呆れたように目を閉じて嘆息した。
「無理をして敬語を使わなくて結構よ。あなたの方が年上で、しかも私はもうあなたの上司ではないのだから」
(上司……)
年下の元上司。なるほど、それならばミリーの態度も、慇懃無礼ともいえる物言いもしっくりくる。
ミルカが一人で納得していると、ミリーは楽しそうに微笑んだ。
「別に上司でなくとも、あなたを尊敬していることには変わりはないけれど。でもそう言うならお言葉に甘えるわ」
口調を戻して言うミリー。
「あたしがあなたのことを追いかけていたのは知っていたんでしょう?」
「……ええ。ラディスカリ総評議長にもお話を伺っていたわ。私のことをいろいろ調べたり、私が作ったものを収集しているのも知ってる。目的はわからないけれど」
「だから、あなたを尊敬しているからよ?」
「…その言葉を真に受け取れと本気で言うつもり?」
わずかに不快そうに、ミシェル。
「私が去った後、てっきりあなたが議長職を務めてくれていると思っていたのだけれど。あなたの実力ならば十分に務まると思っていたからこそ、あなたを後継に指名したのよ」
「ええ、その評価は純粋に光栄だわ。けれど後継への指名そのものには興味なかったの。あたしも早々にその座を譲って辞めたわ」
「……何故」
理解できない、という様子のミシェルに、ミリーはにこりと笑みを深めた。
「あなたのいない世界に、興味なんてないもの。あなたに挑んで、実力で勝つことがあたしの目標で、それ以外のものはいらないの」
「………」
その理由は少なからずミシェルにとっては衝撃だったようだった。仮面のようだった無表情から、少しだけ目を見開いて絶句している。
沈黙が落ちたところで、ミルカはようやく、おずおずと口をはさんだ。
「……あの」
「なに?」
ゆったりと問い返すミリー。
「わたし、お邪魔じゃないですか?ていうか、なんでわたしが連れてこられたんでしょう?ミシェルに会えたのは嬉しいけど……正直混乱してて」
ミルカは肩を竦めて、続けた。
「いっぱい聞きたいことはあるけど、聞いていいものなのかもわからないし。二人の事情だから口出しできる立場でもないけど、ミリー先生も……たぶんミシェルも、その会話をわざわざわたしに聞かせるっていうことは、何かの意味があるんだと思います。でも、それが何なのか全然わからない」
「……へえ」
ミルカの言葉に、ミリーは興味深げに表情を広げた。それから、先生が生徒を褒めるように、にこり、と元気づけるような笑みを投げる。
「ミルカちゃん、魔道士になろうと思ったきかっけは、故郷の村が魔物に襲われたのを助けてくれた魔道士だって言ってたそうね」
「……はい、まあ」
ミリーに直接話したわけではないが、話したフィズはミリーの養子だ。話が伝わるのもおかしなことではない。
素直にうなずいたミルカに、ミリーはゆっくりと続けた。
「ミルカちゃんが子供の頃。入学書類に記載されていた、ミルカちゃんの故郷。魔物に襲われ、甚大な被害があり、それでもそれを救った魔道士が故郷の復興まで手伝った……その話と、あたしが追っていた、彼女…ミシェルの足取りとを合わせれば、その魔道士がミシェルなんじゃないかってことは予想がついていたの」
「じゃあ…ミシェルの行方が分かったから、わたしを連れてきてくれたってことですか?」
よくわからない、というように、ミルカ。
というのも、ミリーがそんな温情的なことをするというのがどうにもしっくりこないからだ。恩人ならば自分で探せ、と、いかにも彼女なら言いそうである。
事実、それを肯定するようにミリーは笑みを深めた。
「それだけだったなら、ミルカちゃんが一人で見つけるべきだと思うわね。見つけ出す手掛かりくらいはあげたかもしれないけど」
「……じゃあ、なんで」
「……そろそろ、頃合いかしらと思ってね」
ミリーは自分に言い聞かせるように言うと、再度ミシェルを見た。
ゆっくりと。
ミシェルだけでなく、ミルカにも理解できるように、告げる。
「……ミルカちゃんの力を封印したのは、あなたね?」
しばらく、意味が理解できなかった。
ミルカちゃんの力。
封印。
いつもの彼女ならばすぐに結びつきそうなそのワードは、彼女の頭を真っ白にするばかりで。
「……え、と……?」
胸に沸いたのは、混乱と、わずかな不安。
この話を聞いてはいけない、という、漠然とした。
「おかしいとは思っていたのよね」
ミリーはなおもミシェルを見つめながら、続けた。
「確かにミルカちゃんの魔力は膨大で、慣れていなければコントロールも難しい。小さい出口に力が集中して暴発するのも不思議じゃないわ。でもいくら練習しても、知識をつけても、レッスンを受けても、この子のコントロールは一向に上達しなかった。普通は、訓練することで出口が広がって、だんだんとうまくいくようになるものよ。でも彼女には一向にその兆しが見えなかった。普通じゃないわ」
そこで、意味深に一拍置いて。
「彼女に、普通じゃない力がかけられているなら、話は別だけどね」
ゆっくりと。
ミシェルの方を向くと、彼女は相変わらず冷たい無表情で。
それは、その言葉を肯定しているようにも否定しているようにも見えた。
「…そうね」
ミシェルはゆっくりと目を閉じ、そして小さく嘆息した。
「そうするしか手立てがなかった、だからそうした。それだけのことよ」
淡々とした物言いに、言葉が詰まる。
彼女たちの話を総合すれば、ミルカの魔法が上手くいかないのは、ミルカ自身の努力や才能の問題ではない。ここにいるミシェルが、意図的に、ミリーの言い方を借りれば「出口が広がらないように封印した」のだ。
「なんで……」
ぽつり、と無機質な言葉がこぼれる。
不思議と、裏切られた、という気持ちにはならなかった。ただ純粋に、なぜ、という気持ちがわく。
ミシェルは、そこで初めてミルカの方を向いた。
「あなたの魔力は、危険だったの。あなたの魔力につられて、魔物たちが集まってくるほどにね」
「え……」
どきり、とする。
ミシェルは続けた。
「あの魔物たちは、明らかにあなたの魔力を狙っていた。あの頃のあなたには自覚はなかったかもしれないわ。もっとも、自覚する間もないほどすぐに倒してしまったけれど」
「じゃあ……わたしが魔物に襲われないように、封印してくれたっていうこと?」
「それもあるわ」
それ「も」、と意味深な言葉を続けるミシェル。
首をひねるミルカの横で、ミリーが嘆息した。
「災いの芽は摘め、か。あの世界を出ても、あなたの気質はあまり変わらないのね」
「災いの芽…?」
さらに意味が分からずミリーの方を向くミルカ。
ミリーは肩を竦めた。
「つまり、あなたの力が大きすぎて、将来世界を脅かす存在になることを懸念して封印したのよ」
「えぇ?」
あまりに斜め上から来た回答に思わず声を上げる。
ミリーは苦笑した。
「まー今の失敗続きの現状だけならそうなるのも無理はないけど、そもそもあなたの魔力は大きすぎるの、それは説明したでしょう?」
「そうですけど、いまいち実感がないというか…本当にわたしにそんな力があるんですか?」
「フィズといた時には使えたでしょう?あれがあなたの本来の力よ」
「うーん……」
まだ信じられない、というように唸るミルカ。
しかし、ミシェルは別のところが気になったようだった。
「……誰かといた時には使えた、と言った?」
「ええ」
そちらににこりと微笑み返すミリー。
「あたしの息子…もちろん養子だけど。彼がそばにいると、魔力が共鳴してあなたの封印が効かなくなるの」
「…そんなことが……」
ミシェルは眉を寄せて黙り込み、ミリーは楽しそうに続けた。
「もちろん、それが理由で今彼らを引き離しているけどね。可哀想ね、想いが通じ合った恋人同士なのに」
「………」
その言葉は、少なからずミシェルにとっては痛手となる威力があったようだった。無表情だった瞳に、わずかに剣呑とした色が灯る。
二人の間にピリピリとした雰囲気が宿るのを察し、ミルカは慌てて話の軌道を修正した。
「…つ、つまり、ミシェルはわたしの魔力が将来危険になるかもしれないから、わたしがそれ以上魔法が上手くならないように封印した、でもフィズがそばにいるとその封印が解けるばかりか、本来の実力以上に魔力が放たれてしまう、ということですか」
「整理するとそういうことよ」
「なるほど……じゃあ、なんていうか、仕方ないですね」
「仕方ない?」
彼女の言葉が意外だったのか、首をかしげるミリー。
ミルカは頷いて続けた。
「ミリー先生とミシェルが以前どういうところにいたのかは聞かないし聞く気もないけど、きっと…なんていうか、わたしたちとは違う世界にいたんですよね?それこそ、今そこに魔物がいたから倒すとか、そういう小さなレベルじゃなくて…もっと大きな、高い所から、わたしたち全体を見渡すような、そういう場所に。…あ、YesともNoとも言わなくていいです、わたしの勝手な想像なんで」
ミルカの言葉を2人は黙って聞いている。
「だとすると、ミシェルがわたしを助けてくれたのは、わたしの村が危険だったからじゃなくて…わたしが危険だったから。わたしがあのままあそこで暮らしていたら、村を破壊するのは魔物じゃなくてわたしだったかもしれなかった。村を破壊してしまったわたしのこころが壊れて、世界を脅かすかもしれなかった。だからミシェルはわたしを助けて、わたしの魔力を封印した」
ミシェルは黙ってミルカの話を聞き、肯定も否定もしない。
ミルカはそんな彼女に向かって、にこりと微笑みかけた。
「なら、やっぱりミシェルのやったことは、ミシェルの立場なら仕方ないことだし、むしろわたしの力を封印したことはミシェルの優しさだと思うわ。あらためて、ありがとう」
「ミシェルの優しさ?なぜ?」
ミリーが尋ねると、ミルカは当然というようにそちらを向いて答えた。
「だって、わたしが危険なら、一番の危機回避はわたしを殺すことでしょ?」
今度こそ、ミリーとミシェルが絶句した。
ミルカはどうということはない様子で、続ける。
「わたしが、とか、村が、とかじゃなくて、世界全体が平和に、っていうことを考えた時に、イレギュラーであって排除されるべきなのはわたし。それを押して、ミシェルはわたしを助けてくれた。結果としてわたしの可能性を狭めることになったけど、わたしは確かに救われたんだと思うわ。だから、ありがとう」
「………」
再びにこりと微笑んだミルカに、ミシェルは押し黙った。
その無表情には、喜びとも後悔ともつかぬ複雑な色が混じっているように見える。
「わたしね」
ミルカはその瞳をまっすぐ見つめて、さらに続けた。
「ミシェルみたいな魔道士になりたくて、村を出て魔道学校に通うことにしたの。魔法なんて全然使えなかったし、両親にはすごく反対されたけど…頑張って説得して。
今、この話を聞いて…でも、わたしはやっぱりミシェルみたいな魔道士になりたいと思うわ。
あなたみたいな、奇跡を起こす魔道士に」
「……奇跡?」
「ええ!」
いぶかしげなミシェルに、嬉しそうに微笑み返して。
「ミシェルは奇跡のように、わたしを魔物から救い出してくれて、めちゃくちゃになった村をあっという間に直してくれた。それだけじゃない、もっと大きな、もっと遠くを見て、あらゆる可能性からわたしを一番いい所へ導いてくれた。それが、わたしの力を封印することだったとしても、わたしはそれが正しいと思うわ。
だから、わたしもなりたいの。ミシェルみたいに、あらゆるものが見えていて、あらゆる可能性から最善を探し出して、それを実行できる魔道士に。
それはきっと、わたしみたいに普通の人間からしてみたら、奇跡に見えると思うわ」
ミシェルを一目見て駆け寄った時と同じ、きらきらとした、憧憬をたたえた瞳で。
「わたしは、奇跡を起こす魔道士になりたい。だから、ミシェルにわたしの封印を解いてほしいの」
沈黙が落ちる。
ミシェルはしばらく黙った後、ミリーの方を見た。
「……あなたはどう思うの?」
「あら、あたしの意見を求められるとは思わなかったわ」
「あなたは彼女が通う学校の校長でしょう?私より彼女のことをよく知っているわ」
「まあ、よく知っているというほどたくさん教えたわけでもないけど…でも、今のこの子の言葉がすべてね」
やられた、とでもいうような、少し悔しげな苦笑をミルカに投げるミリー。
「この子は、その力を操るにふさわしい、強い心と深い思慮がある。目標のためにどんなに遠くても諦めない強さがある。
あなたが懸念するような、世界の脅威となる存在にはならないと、あたしなら思うわね」
「……不本意だけど、同意するわ」
ミシェルはそう言うと、立ち上がってミルカの傍まで歩いてきた。
「……私がかけた枷は外すわ。でもそれは、あなた本来の力に戻すということ。その大きな魔力を使いこなすには、まだまだトレーニングが必要になるわ」
「承知の上よ!」
両こぶしを握り締めて意気込みを示すミルカ。
そこで、ミシェルは初めて、仕方なさそうな、弱い笑みを見せた。
「……あなたの意思を無視して、力を制限して……ごめんなさい」
その笑みは、最初の張り付いたような、作り物の笑顔とは違う。彼女本来の、心から出た笑みのように見えた。
「あなたなら……その大きな力を使いこなして、きっと世に名を遺す魔道士になる。
……奇跡を起こせる、魔道士に」
「!……」
その言葉に大きく目を見開くミルカ。
にこり、と、ミシェルは優しく微笑んで見せた。
「彼女ほどではないけれど。私も何か力になれることがあるなら、いつでも会いに来て。
あなたは私の、もう一人の娘のようなものだから」
「………はい!」
勢いよく頷き返すミルカの額に、ミシェルはそっとその手のひらを重ねた。
そして、再会
「アクア・クリエイト!」
ぱしゃん。
ミルカの呪文と共に、空中から水が湧き出て地面へとこぼれていく。
ミルカはそれを満足げに見下ろして、それから嬉しそうに両手を上げた。
「やっっったーー!!」
改めて、魔法が使える、と実感する。
かつてはフィズがそばにいた時だけに感じた、自分の中からするりと大きな力が流れ出ていく感覚。あの時と比べて少なくはあるけれど、いま彼女は間違いなく、自分だけの力で魔法を使えていた。
「♪~~♪~~」
上機嫌で再び歩き出すミルカ。
行先は、中央広場。
「…じゃあ、わたし本当にお使いに行かされるんじゃないんですね?!」
「だから、そう言ってるでしょうが。疑り深い女はみっともないわよ」
「誰のせいだと……ミリー先生はこの後は?」
「積もる話もあるし、あたしはもう少しミシェルとここで話していくわ」
「…私にはないけれど」
「まあそう言わない。ミルカちゃんは中央広場のステージでも見てきたら?」
「中央広場…ですか?」
「ええ。マヒンダから来た魔術師ギルド総本山のメンバーが順にショーをしているそうだから」
「魔術師ギルドの……」
「もちろん、フィズも手伝いとしてそこにいるわよ」
「!……いいんですか?」
「良くなければ、わざわざミシェルのところに連れて来ないわよ」
ミリーは上機嫌でにこりと笑うと、ああ、と付け足した。
「祭りが終わるまでに、考えておきなさい。フィズを、フェアルーフに呼び戻すかどうか」
「どういうこと……話がうますぎない…?」
これまでのあれやこれやですっかり疑い深くなっているミルカ。
「いくら最後だからってこんなにいいことばかりあっていいものかしら…伏線回収祭り?」
はいメタ禁止。
「はー……フィズが帰ってくる、かぁ」
改めて言って、息をつく。
願ってもないことだった。想いを自覚してほぼすぐに引き離され、想い合えているという実感もなしに手紙と音声映像だけのやり取りとなってしまった。毎日のように手紙のやり取りはしているけれど、やはり足りない、寂しい、という気持ちはいつも付きまとう。直接触れ合える以上の幸福などありはしないのだ。
だが。
「整理しよっか……そもそもの始まりは、わたしの村が魔物に襲われたことで……なんで襲われたか、その当時はわかってなかったけど、実は大きすぎるわたしの魔力を狙ってきた……うーん、自分で言うと中二病患者のようだわ」
実のところ、そんなことを言われても実感がない、というのがまだ正直なところだ。なにせ、彼女の魔法はこれまでほとんどうまくいかなかったのだから。だが、ミシェルとミリーが口を揃えて言うのだから事実なのだろう、と思う。
「それで、ミシェルはその魔物を倒し、村の復興を手伝って…そもそもの原因となったわたしの魔力を、これ以上外に出ないように封印した。だからわたしが魔法を使おうとすると、大きな魔力が小さな出口に殺到して爆発するようになってしまった」
うんうん、と頷きながら、順序だてて整理するミルカ。
「でも、わたしがフィズと出会って……何故か、彼がそばにいると魔法が上手くいくことが分かった。それも、普通ではありえないほどの威力で。ミリー先生によれば、魔力が共鳴して、わたしの魔力の出口が大きく開いてしまうから…ミシェルの封印も役に立たないほどに。
それは悪いことではないけど、リスクもある。魔力が暴走して、コントロールが効かなくなってしまった時…どんな被害が出るかわからない」
ぐ、と両手を握り締めて、ミルカは自分に言い聞かせるように呟いた。
よく、知っている。
あの時は奇跡的にあたりに無関係な人間はいなかったが、フィズがならず者に殺されてしまったと思った瞬間……頭が真っ白になって、気づけばあたり一面の建物が粉々になっていた。
瀕死のならず者はミリーによって一命をとりとめ、回復されて捕らえられたが…自分で自分の力を制御できない恐怖は、今も彼女の脳裏にこびりついている。
「………」
ぎゅ、と、自分の体を抱きしめるように腕を寄せる。
フィズが帰ってくるのは嬉しい。
魔法が使えるようになったことも。
これからは二人で、自由になった魔力をさらに鍛え、ともに力を高めあっていける。
「………それで、いいのかしら」
するりと、素直な気持ちが口に出た。
お姫様の呪いは解け、王子様と再びめぐり逢い、2人は幸せになりました。めでたし、めでたし。
……本当に?
軽やかだった足取りが、だんだんと重くなり、そして立ち止まる。
いつの間にか、陽もだいぶ落ちて、あたりは薄暗くなりかけていた。
遠くで爆発音がうっすらとする。何かの出し物か、あるいは中央広場のステージの演出だろうか。
このまままっすぐ行けば、中央広場に着く。眠れぬほどに恋い焦がれた愛しい人が、すぐそこにいる。
だが、ミルカの足は縫い留められたようにそこから動けなくなっていた。
遠くに見える中央広場の喧騒が、だんだん薄くなっていくような心もちさえして……
すると。
「おい!こんなところでどうした、迷子か?」
下から響いた声に、催眠術から解けたように急激に意識が引き戻される。
慌てて見下ろすと、そこには彼女より背が低い少年が、仁王立ちして彼女を見上げていた。
「え……と?」
「なんだ、迷子じゃないのか?中央広場のステージ、見に来た、違うのか?」
「違わないけど…違う、かな?」
なんだかよくわからないが、少年の問いかけに、ミルカは素直な気持ちを苦笑に乗せて返す。
彼女より背が低いということは、まだ13~14歳程度だろうか。このあたりに住む人間ではないのか、シェリダンの民が着るような異国風の装束を身に纏っている。肌はこれもシェリダンの民のような、日に焼けた砂のような色に、白茶けた短い髪。何より目を引くのは、左目の大きな眼帯と、それをものともしない強い光を宿した赤い右目。
今はその右目は、先ほどの禅問答のようなミルカの回答に困惑の色をたたえている。
「違わないけど違う?よくわからない。人間の言うこと、難しい」
「えっと…あなたこそ、迷子じゃないの?親御さんは?」
「親、いない。オレ、見回りしてる」
「見回り?」
首をひねるミルカ。少年は頷いた。
「会場の周り、怪しい奴いないか、見回り。祭り、みんな浮かれる、ハメ外すやついる、言われた。そういう奴いたら、報告する、オレの役目」
若干カタコトの口調で、彼は淡々とそう言った。先ほどの「人間の言うこと」という発言といい、もしかしたら彼は人間ではないのかもしれない。
それは特に気にせず、ミルカは話を続けた。
「じゃあ、迷子はあなたの報告対象じゃないのね。わたしがここまでくる間にも、特に怪しい人も、ハメ外して迷惑かけてるような人もいなかったわよ」
「そうか、ならよかった」
にかっ、という擬音語が似合う笑い方で、少年はミルカに笑いかけた。
ふっと力が抜け、ミルカは彼に微笑みかける。
「ご苦労様。わたしは迷子じゃないけど……ステージまで連れて行ってくれる?」
「いいぞ!オレ、案内する!」
彼はそう言って、先導するようにステージの方を指さした。
「ついてこい!」
ミルカは先ほどよりは幾分浮上した気持ちで、彼の後について歩きだした。
「会場の見回りっていうことは、あなたは魔術師ギルドの関係者なの?」
前を行く少年に話題を振ると、彼は前を見たまま頷いた。
「カンケーシャ、よくわからない。オレ、手伝い」
「手伝いって…あなた」
言葉を続けようとして、そういえば名前を聞いていなかったことを思い出す。
「いつまでもあなたじゃ不便ね。わたし、ミルカよ。あなたは?」
「オレ、リジー!」
ぱっと嬉しそうな顔をして、リジーと名乗った少年はミルカの方を向いた。
「オマエ、ミルカ、覚えた!」
「ありがとう。リジー……どこかで聞いたことがあるような?」
首をひねるが、すぐに思い当たることはない。とりあえず記憶を手繰ることはあきらめ、先ほどの質問に戻る。
「リジーは、魔術師ギルドの人じゃないのね?お手伝いなの?」
「そうだ。手伝いの、手伝い」
「手伝いの手伝い?」
「オレ、世話になってるヤツ、いる。そいつも、ギルドのやつ、違う。でも、手伝え、言われた。オレ、それ、手伝ってる」
「世話になってる人……」
「いいヤツ!」
リジーはまたぱっと嬉しそうに笑った。
「リジー、名前、そいつがくれた」
「名前…付けてくれたの?」
「そう。オレ、昔、名前なかった。魔物だった」
「えっ……」
ぎょっとするミルカ。
リジーは気にすることなく続けた。
「そいつ、オレを魔物からひとにした。ひとになったオレ、世話してくれてる。言葉も、魔法も、全部教えてくれた。いいヤツ。オレ、そいつの力になりたい」
「ああ……」
どこかで聞いた名前と記憶の糸が繋がる。
彼の手紙に書いてあった名前。
「リジーは……その人に魔法を教わって、よかったと思う?」
「思うぞ!マヒンダ、魔法ないと、暮らしていく、難しい、言ってた。オレもそう思う。オレ、ひとになった、けど、魔物の魔力、まだある。うまく使いこなす、大事」
「使いこなす……」
どきりとする。
「……リジーは…もう、魔法はうまく使えるの?」
「全然!失敗ばっかだ」
やはりからっと笑って、リジーは言った。
「魔物の魔力、大きい、ひと、使いこなす、難しい、言ってた。でも、オレ、がんばる」
「そうね…」
「がんばって、魔法うまくなって、早くひとりだち、する。認める、させたい」
「…認める?」
「いいヤツ、オレを、ひとにしたこと、気にしてる。オレ、わかる。だから、早く、ひとりで、なんでもできる、なりたい。
…認める、少し違う。言葉、難しい」
うーん、と眉を寄せてから。はっと思いついたように表情を広げて。
「対等!対等、なりたい」
「対等……」
「そう!そいついない、生きていけない、対等、違う。オレ、ひとりで、生きていける、なったら、そいつの助けになれる。助けになれる、そいつ、オレにしたこと、気にしなくなる。だから、力、欲しい」
「ああ……」
先ほどまで胸にわだかまっていた正体不明の何かが、ようやく、腑に落ちた。
魔法が使えるようになって。彼がわたしの元に戻ってきて。
彼がいれば、わたしは大きな力を使いこなすことが出来る。
でもそれは、彼に寄りかかって生きていくだけ。
わたしの望む結末では、ない。
「リジー!」
少年の向こうから、彼に呼びかける声がする。
最後に聞いたのはもうずいぶん前の……それでも、決して忘れることのない、その声。
「フィズ!」
リジーは嬉しそうに、声の主の元へ走り出した。
「フィズ、あやしいやつ、いなかったぞ!」
「そう。でもこんなところまで来なくてよかったのに。見回りの場所にいないから、心配したよ」
「ヒマだった、ちょっと遠出した。でも、迷子、見つけたぞ」
「迷子…?」
リジーの報告を受け、彼がこちらに視線をよこす。
その瞳が大きく見開かれた。
「……ミルカ……」
ミルカは苦笑しながらそちらへ歩み寄る。
「迷子じゃないって言ってるのに……」
呆然とするフィズの正面で足を止めて、とびきりの笑顔を浮かべた。
「おかえりなさい、フィズ」
その言葉にようやく実感がわいた様子で、彼もまた嬉しそうに破顔する。
「……ただいま、ミルカ」
にこにことやり取りをする二人を、リジーが驚いた様子で見比べた。
「フィズ、ミルカ、知り合いか?」
「いつも話しているでしょう?手紙の彼女だよ」
「ああ!ミルカ、どこかで聞いた名前、思った!そうか!」
またぱっと表情を広げて、リジーは改めてミルカに向き直る。
「フィズ、いつも、オマエの話、してた!オレ知ってる、のろけ、言う!」
「り、リジー……誰からそんな言葉を教わったの」
「マリーだ!」
「やっぱりか……」
フィズは少し赤い顔をして嘆息し、それからリジーの頭を撫でた。
「リジー、ステージはもう終わるから、いったんバックステージに戻っていいよ。今日はもうそのまま、宿に戻って。屋台とか、寄り道してもいいけど、セイカかアスについていてもらって」
「わかった!フィズはどうする?」
「私はミルカと話をするから。遅くなると思うけど、先に寝てていいよ」
「わかった!別に、帰ってこなくてもいいぞ!」
「……だからどこでそういう言葉を……」
「じゃあな!ミルカも!」
「ええ、またね、リジー」
元気よく手を振りながらステージの方へ走っていくリジーに、ミルカも笑顔で手を振り返す。
その姿が見えなくなってから、ミルカは改めてフィズを見上げた。
「あの子がリジーなのね。フィズのこと、すごく慕ってたわよ」
「ギルドでも可愛がられていてね。マリー様が余計なことまで教えるから困るよ……」
まだ少し頬を赤くして頭を掻くフィズ。
ミルカはくすっと笑ってその手を取った。
「もうステージは終わりなのよね?じゃあ、少しお祭りを見て回らない?」
「…そうだね、そうしよう」
フィズも嬉しそうに微笑み、その手を握り返す。
そうして、2人は夜の祭りへと再び歩き出していった。
「はー楽しかった…!」
ストゥルーの刻もだいぶ過ぎ、ライラの刻に差し掛かるころ。
ようやく今日の祭りも店じまいを始め、ミルカとフィズは静けさを取り戻した街並みを歩いていた。
「今日一日でバザールはだいぶ満喫したわ。いろんな人とも回れたし」
「カイたちと回ったの?」
「カイとは少しだけ。本当はパスティやこはくたちとも回るつもりだったんだけど、いろいろ予定が合わなくなっちゃって。でもその分、普段会うことの無い人たちとも会えたし、結果オーライだったわ」
「普段会うことの無い人たち?」
「そう。ほら、ザフィルスの事件の時に知り合った、クローネ。覚えてる?」
「ああ、ミケのお兄さんだよね」
「そう!クローネと、その妹さんとも初めて会ってね、ちょっと一緒に回ったの。妹さんもすごくかわいくてね、美形一家ってすごいわー」
「カイはその時は一緒にいなかったの?」
「カイは早々に別行動したわ。二人の邪魔しても悪いし」
「邪魔…?」
「婚約者と一緒だったのよ。わたしも初めて紹介してもらったわ」
「そういえば、そんなことを言っていたね。私も会ってみたかったな、あの彼女の婚約者なんて、想像がつかないよ」
「それがさー、びっくりするくらいナヨナヨしてるの!おどおどしてて、カイと正反対」
「それは……意外だね」
「でも、カイより強いんだって」
「それを聞いて納得したけど、さらに想像がつかなくなったよ」
「あはは。でも、カイのことすっごく好きみたい。だからなんかちょっと、安心しちゃった。どんな性格でも、どんな家でも、愛さえあれば乗り越えていけると思うもの」
「そうだね、私の母…実母も、女は愛された方が幸せだとよく言っていたよ」
フィズは言ってから、ミルカとつないでいた手を上げ、つないだまま彼女の頬に指の背で触れた。
「……その点、ミルカは心配ないね」
ぐわ。
突然の甘いセリフにミルカが絶句して頬を染めると。
ぐわ。
時間差で、フィズの頬も同じように染まる。
「……また自分のセリフに照れてる」
「はは……照れるつもりで言うわけではないのだけれど」
「つまり天然タラシということね」
「失礼だな。私はミルカ以外にこんなことは言わないよ」
「そーゆーとこよ」
繋いでいない方の手でぱたぱたと顔を仰ぎながら、それでもミルカは久しぶりに彼と話すことの心地よさを感じていた。
手紙とは違う、即座のレスポンス。長く隔てられた距離と時間を感じさせないやりとり。
正直、再会した時も、もっと胸にこみあげるものがあると思っていた。涙を浮かべて彼に駆け寄り、勢いよく抱き着くくらいはするものだと。
けれど、実際再会して、まずついて出たのは、おかえり、ただいま、というごく普通のやり取り。
まるで、今朝出かけた恋人を出迎えた、というような。
それは、離れている時間と距離など問題にならないくらいに、彼がいい意味で「自分の一部」になっていることの証のように思える。
「あのね、フィズ」
「うん?」
「覚えてる?わたしが、魔道士になろうって思ったきっかけのこと」
唐突な話に、フィズは一瞬きょとんとして…それからすぐに、薄く微笑んだ。
「覚えているよ。魔物に襲われたミルカの村を、助けてくれた魔道士がいたのだったね」
「そう。今日ね、わたし、その人に会えたの」
「へえ!それは…良かったね…!」
フィズは彼女の話に驚き、しかし自分のことのように嬉しそうに祝福してくれた。
ふふ、と微笑み返し、続ける。
「それがね、びっくりなの!ミリー先生の知り合いだったのよ!」
「義母の?」
こちらの方も相当驚いたらしい。意外そうに眼を見開いている。
「それは……世間は狭いものだね。でも……うん、義母ならそんなすごい人と知り合いでもおかしくないな…」
「でしょ、びっくりだけど、なんか納得しちゃうっていうか。詳しくは聞いてないけど、元上司…みたい」
「上司って、義母が?」
「ううん、逆なの。ミシェル…あ、その魔道士さんね。ミシェルが、ミリー先生の、上司だったみたいよ。わたし、ミリー先生が敬語使うの初めて見たわ」
「それは…私も聞いたことが無いな。あの義母が敬う相手か……」
フィズも興味津々の様子で話を聞いている。
ミルカは続けた。
「ミシェルを見つけてくれたのは、ミリー先生なの。どうも、ミリー先生がミシェルを追いかけてて、いろいろ情報収集をしていたみたい。それで、フィズからわたしの話を聞いて、その魔道士はミシェルなんじゃないかって思ってたんですって」
「義母が……ミルカのために、ミシェルを探してくれた、ということ?」
不思議そうに、フィズ。
それは、彼もまた、義母であるミリーの人となりをよく知っていて、ミルカと同じように、ミリーがそのようなことをするはずのない人物であると認識しているからに他ならない。
自分たちの認識が同じであったことをくすぐったく思いながら、ミルカは続けた。
「半分あたりで、半分はずれ、かな。ミリー先生はミリー先生で、ミシェルをずっと追いかけていたみたい。
わたしを連れてきてくれたのは……わたしにかけられた封印を、解いてもらうためだったの」
「……封印?」
いぶかしげに眉を寄せるフィズ。
ミルカはうなずいた。
「わたしの魔法が、フィズがいない時に上手くいかないのは……ミシェルが、わたしの魔力を封じていたからだったの」
「…どういうこと?」
やや険しい表情となるフィズに、ミルカは苦笑して事情を説明した。
「ミリー先生も言ってたでしょ?わたしの魔力は大きすぎる、って。全然実感ないんだけど……でも、わたしの村を襲った魔物は、わたしの魔力を狙ってきていたんですって。だから、わたしがこれ以上魔物に狙われないようにするために……それと」
これも言わなければフェアではない、というように、慎重に付け足す。
「…わたしが、大きすぎる魔力に狂って、魔物にならないように。ミシェルは、わたしの魔力を封じ込めた」
「………」
フィズは黙ってミルカの話を聞いている。
「ミリー先生は、頃合いだ、って言ってたわ。フィズと離れて、わたしにいろいろとお使いを頼んで、いろんな経験をさせて。相変わらず魔法は使えないけど、ミリー先生の中で、ミシェルに封印を解くよう説得してもいい、一定のラインをわたしが超えたんだと思うの」
「……そう」
フィズはその言葉に嬉しそうに目を細めた。
「義母がミルカに課していた、いろいろなことの意味を、ミルカはちゃんと理解していたんだね」
「そりゃあね。邪魔ばかりしてるように見えるけど、そうじゃないことくらいはわかるわ」
苦笑を返すミルカ。
「ミリー先生も、ミシェルと同じ。わたしたちよりもずっと、高い所から、広い世界を見渡して、そして最善を選び取ることが出来るひとなんだと思うわ。だから、ミリー先生のすることに無意味なことなんてない。今回のことも、わたしを認めてもらった、と思っていいんだと思う」
「そうだね。私もそう思うよ」
「ミシェルにお願いして、わたしの封印を解いてもらったの。今はフィズと一緒にいるから証明できないけど……ひとりで魔法を使えることも、もう確かめたわ」
「そう。……おめでとう」
にこり。
ミシェルに会えた、と言った時と同じように、まるで自分のことのように嬉しそうに微笑む恋人。
ミルカは嬉しそうな、そして少し切なげな笑みを彼に返して、ずっと握っていた彼の手を離し、大きく二歩、三歩と歩みを進めた。
「……ミルカ?」
離された手を所在無げに握って、首をかしげる彼。
いつの間にか、魔道学校の門にたどり着いていた。
門の前で、くるりと彼を振り向く。
「ミリー先生、わたしに言ったの。フィズをフェアルーフに帰すか、決めておきなさいって」
「!………」
ミルカの言葉に、フィズは大きく目を見開いた。
沈黙が落ちる。
黙ったままお互いを見つめあう恋人たちは、しかし今は、幸せではなく、張り詰めたような空気をたたえていた。
「……それで、ミルカは何て答えるの?」
ゆっくりと。
彼女の真意を探るように、真剣な表情で問うフィズ。
ミルカは目を閉じて俯いた。
「…最初は、嬉しい、って思ったわ。フィズとずっと一緒にいられる。もう魔法も使える。しかもフィズと一緒にいれば、わたしは大きな力を使うことが出来る」
「……そうだね」
「でも、そうじゃない。わたしが魔法を使えるようになっても、わたしとフィズが離れていきゃいけない根本的な原因は、何一つ解消されてない」
そう。
なぜ、ミリーが二人を引き離したか。
フィズといることで、大きく開いた魔力の出口は…コントロールを失えば、大惨事を引き起こしかねない。
それは、ミシェルの封印が解けたところで、まったく解消されていないことなのだ。
「ミリー先生も、ほんっとに意地が悪いんだから。わたしが何て答えても、きっとフィズはマヒンダに帰されるんだわ」
苦笑して言うミルカに、フィズも同じように苦笑を返す。
「それでも、義母はミルカの口から答えを聞きたいのだと思うよ」
「……そうね」
目を開けて。
正面から、彼の顔を見返す。
もうすぐ、再び会えなくなってしまう、愛しいひとの顔を。
「リジーがね、言ってたの」
「リジーが?」
「フィズは、リジーをひとにしたことを気にしてるって。だから、早く魔法が使えるようになって、独り立ちをして、フィズと対等になりたいって。対等になって、フィズの助けになれば、フィズはもう気にしなくなるって」
「リジーが……そんなことを」
複雑そうに眉を寄せるフィズ。
ミルカはふふっと笑った。
「でもね、わたし、リジーの気持ちがわかるわ」
「……なぜ?」
答えが分かっている、という様子で、それでも問うフィズに、にこりと笑みを返して。
「わたしは、フィズに守ってほしいのでも、支えてほしいのでもないの。
あなたとふたりで、対等に、一緒に歩いていけるわたしになりたい。
そのためには、今、あなたに甘えちゃダメなんだと思う」
「……そう、か」
わずかに寂しそうに。それでも、ミルカが導き出した潔い結論に、フィズは嬉しそうに微笑んだ。
「私も、寂しいけれど。ミルカが夢を叶えるまで、私も己を磨いていくよ。うかうかしていると、置いて行かれそうだから」
「ふふ。じゃあ、競争ね。一人前の魔道士になるまで」
「そうだね」
微笑みあいながら、再び歩み寄る二人。
「……でも、私が帰るまでは……もう少し、私の可愛い恋人でいてくれる?」
彼が、髪の毛一筋をも愛おしむように、そっとその巻き毛に指を絡めれば。
「もちろん。あとちょっとだけど、たくさん甘やかしてね?」
彼女の華奢な指が、離れるのも惜しいというように重なって絡まりあう。
いつの間にか、街の喧騒も消え、校門前のぼんやりとした魔道灯だけがふたりを淡く照らしていた。
あと少しで、再び別れを迎える恋人たちの影が、今を惜しむように一つに重なってゆく。
いつの日か。
奇跡を起こす魔道士になって、胸を張って彼の隣に立つ、その日を夢見て。
手の届かない場所にいることはわかってる。 その場所に行くためには、たくさんの努力が必要なことも。 けど。 わたしは、何一つあきらめない。 だって、わたしは知ってるもの。 あきらめなければ、いつか必ず奇跡が起こることを。
“Last Ceremony of Mirca Arredina” 2021.8.10.Nagi Kirikawa