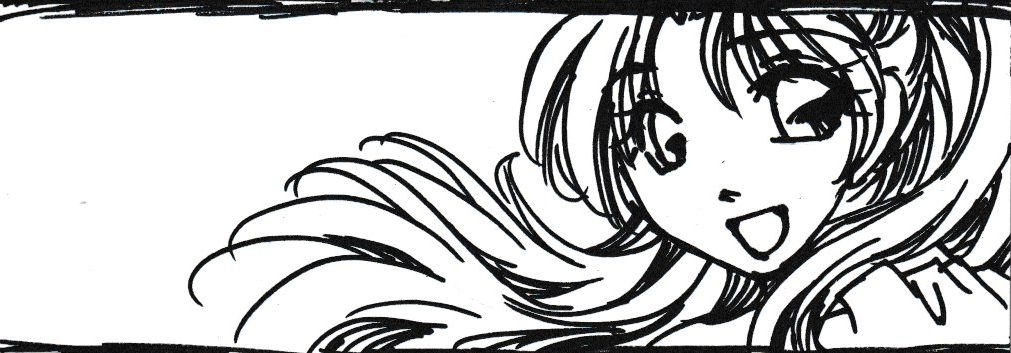
Letisia Lude
ずっとずっと好きだったの。 好きじゃなかった時のことなんて思い出せないくらいに。 この気持ちは、ずっとあなたに届かなかったけれど。 フラれて気まずくなっちゃうのも怖くて、それ以上強くも押せなかった。 でも、もう会えなくなるかもしれないなら。 このまま気持ちに蓋をして、ずっと後悔するよりも。 フラれたって、自分の気持ちをまっすぐ伝えなきゃ。
突然の知らせと、励ましの声
「うそ………」
その手紙を読んだレティシアの表情から、手紙の内容が彼女にとって喜ばしいものでないことは容易に想像がついた。
「速達」の印が押された封筒。いつものように朝食を食べようとした彼女に、定宿の女将が食事と共に差し出したものだ。
差出人はエリオット・ルード。故郷マヒンダに住む、彼女の一番上の兄。
エリオットの手紙は今に始まったことではない。若干シスコン気味のこの兄は、彼女を連れ戻しに来たこともあるくらいには妹に対して過保護気味だ。
手紙の内容も大体最後は「そろそろ家に帰っておいで」で締めくくられる。
レティシアの両親が経営する食堂は、嬉しいことに昔も今も繁盛しているが、その代わりに子供の事はほぼほったらかしだった。
エリオットはそんな両親の代わりにレティシアを育ててくれた、いわば親代わりの存在だ。過保護になるのも無理からぬことだろう。
レティシアが魔道学校に通うと言った時も、冒険者になりたいと言った時も、猛反対だった。
半ば強引に、家出のような形で冒険者となったレティシアを、追いかけてきて連れ戻そうとしたこともあったが…レティシアが冒険者として真摯に頑張っている姿と、仲間からの説得とで一応納得し、冒険者を続けられることになった。『最低月に1度は手紙を書く事』と『半年に一度は里帰りすること』という条件付きで。
帰省…はタイミングが合わずに見送ることもあったが、手紙はきちんと書いていた。いつもの里帰り催促…かとは思ったが、わざわざ速達で届いたことに胸騒ぎを覚え、朝食もそこそこに封を開けると。
いつも見る、エリオットの字。いつもよりかはずいぶん短い文章。最後に締めくくられる「帰っておいで」のメッセージ。
だが、いつもと違ったのは。
『ルティアは、もう長くない。残りの時間を一緒に過ごそう。…帰っておいで』
ルティア。
レティシアのすぐ上の兄。
生まれつき体が弱く、レティシアが物心つく頃にはすでに寝たきりの状態だった。
外に出ることもできず、共に遊んだ記憶はない。レティシアたちが外で遊ぶのを、ルティアはいつも部屋の窓から眺めていた。
「ルティアにいちゃんは、わたしたちといっしょにおそとであそばないの?」
幼いころ、ルティアの部屋で、そんな質問をしたことがあった。
まだものの道理もわからない妹の質問に、こちらもまだ幼いルティアは苦笑してレティシアの頭を撫でた。
「いっしょにあそびたいけど、そうするとおねつがでちゃうからダメなんだって。でも、レティシアたちがたのしそうにあそんでるのを見るのはすきだよ。だから、レティシアがたのしかったことを、おはなししてくれるとうれしいな」
そう、ルティアが言うから。レティシアは毎日のことをルティアに楽しく話して聞かせるのが日課になっていた。
「ルティア…兄ちゃん……」
食べかけの朝食がすっかり冷えて硬くなってしまっても、レティシアは手紙から目を離すことができず呆然と呟いた。
何度読んでも、短い手紙の文面は変わらない。しかし、何度読んでも、短い文が頭をすり抜けて出て行ってしまうような感覚に陥る。
かさり。
レティシアはのろのろと手紙を封筒に戻すと、すっかり冷めきった朝食を機械的に口に入れ…全く味がしなくて結局残してしまった。
「なんだい、残しちゃうのかい?……顔が青いよ、大丈夫かい、レティシアちゃん?」
宿の女将が心配そうに顔をのぞき込む。
そちらに何とか苦笑を返すと、レティシアは手紙を持って部屋に戻った。
「ここはレティの家なんだから、いつだって帰ってきていいんだよ」
旅立ちの日。
もう帰ってこられないかもしれない、と逡巡したレティシアに、ルティアは幼いころのようにレティシアの頭を撫でてそう言った。
「レティがやりたい事をして欲しい。そして、レティが冒険者として見てきた事、体験した事を僕に聞かせて」
「……わかった。行ってくるね、ルティア兄ちゃん…!」
涙目で頷いて、レティシアは家を出た。
わかっていたはずだった。いつかこんな日が来ることが。
わかっていて、家を出た。
だが、いざ現実が目の前に来ると、頭が真っ白でどうしていいかわからない。
かさり。
もう一度手紙を出して中を確認する。
しかし、書かれている文面は何度見ても同じものだ。
『ルティアの主治医が、余命について話してくれた。
今すぐにどうにかなる、というわけではないが…最期は家族揃って一緒に過ごさせてあげたい。
ルティアは、もう長くない。残りの時間を一緒に過ごそう。…帰っておいで』
部屋のベッドから、外で遊ぶレティシアを見守ってくれていた兄。
レティシアが一日の楽しかったことを報告するのを、いつも嬉しそうに聞いてくれた兄。
冒険者になるために家を出るレティシアの背中を、笑顔で押してくれた兄。
その兄と…もうすぐ、会えなくなる。
ぽたり。
広げていた手紙に涙が一粒こぼれて、いつもより幾分か弱々しく綴られた文字を、そっと滲ませた。
「継承祭……にぎやかだな」
それから、レティシアは着替えて外に出た。
本当はすぐにでもマヒンダ行きの船に乗るべきだったろう。しかし、突然訪れた事実に混乱しすぎて考えがまとまらない。
今は、継承祭の賑やかさに気を紛らわせていたかった。
レティシアは街の喧騒を遠くに見ながら、サザミ・ストリートを折れ、通い慣れた喫茶店のドアを開けた。
からん。
ドアベルが響き、中からマスターののんびりとした挨拶が聞こえた。
「いらっしゃーい」
「こんにちは、マスター」
「あ、レティシアちゃん久しぶりー」
「お久しぶり、マスター。ミニウムもお久しぶり」
「レティちゃん、おひさんなのです!」
「……新人さん?」
カウンターにマスターと並んで立つ執事を見て首をかしげると、執事はにこやかに微笑み返した。
「マスターの友人です。たまにお手伝いをさせていただいているんですよ」
「そうなのね。美形の友達はやっぱり美形ね…」
感心したように言い、レティシアはぐるりとあたりを見回した。
すると、カウンターの一番端の席に座っている女性に目を止める。
「あれっ……確か…」
たたた、と小走りで女性のもとに駆け寄り、レティシアは恐る恐る声をかけた。
「こんにちは。プライベートなお時間に失礼します。ミレニアム・シーヴァン様…ですよね?」
声をかけられた女性……ミリーはゆっくりと視線を上げた。
丁寧に礼をするレティシア。
「私、レティシア・ルードっていいます。こうやってご挨拶するのは初めてですが、学園の行事に何度も参加させて頂いています」
「知ってるわ。ウォークラリーに参加してくれたものね?」
ミリーがにこりと微笑み返すと、レティシアは驚いたように目を見開いた。
「えっ…知ってるって」
「うちの子たちが雇った冒険者のデータはすべて目を通しているの。1回目のウォークラリーに、ルキシュと一緒に出てくれたわね。ミケの知り合いでしょう?それも把握しているわ」
「うわ……光栄です!あの、ウォークラリーのほかにも、無料開放された魔法教室では、新しい知識を得る機会を頂いて……とても感謝しています」
「そう言ってくれてあたしも嬉しいわ。あまりかしこまらないで大丈夫よ。ミリーと呼んで頂戴」
「そ、そんな恐れ多い…」
「うちの子たちはみんな『ミリー先生』って呼ぶわ。別にそんな大したことでもないわよ」
「じゃあ……ミリー先生。ありがとうございます。
それにしてもすごいですね、ウォークラリーで雇われた冒険者は全部把握されてるんですか?」
「もちろんよ。これから来る彼女のこともね」
「…彼女?」
レティシアが首をひねったその時。
「すみません、マスター!」
からん。
ドアベルが響き、一人の女性が店に飛び込んでくる。
「すみません、うちの司祭が、こちらのフィギュアをパチって帰ってきていて…!これ、お返しします!」
その女性は足早にマスターに駆け寄ると、持っていたガラスケースを差し出した。
苦笑するマスター。
「あー、無くなったと思ったらやっぱり闇……じゃない、オルーカちゃんとこの司祭様だったかー。ありがとね、オルーカちゃん。大切にしてたものだったから、戻ってきてよかったよ」
「うう、本当にすみません……このお詫びはいずれ必ず正式に……というか、もうあの司祭は出禁にしてくださいね!出禁に!」
「あははー考えとく」
ひらひらと手を振るマスターに、ほっと胸をなでおろす女性。
見覚えのあるその姿に、レティシアは嬉しくなって声をかけた。
「オルーカ、久しぶり!」
レティシアの声に女性……オルーカは振り返って嬉しそうに微笑む。
「レティシアさん!お久しぶりです」
と、レティシアの隣にいるミリーにも気づいたようで。
「そちらは……校長先生ですか?魔道学校の」
「覚えがめでたくて何よりだわ。カイとヘキが雇った冒険者さんね?ミリーでいいわ、よろしく」
「わ、覚えていただけてるなんて光栄です。こちらこそよろしくお願いします」
ぺこりと頭を下げるオルーカ。
「ねえオルーカ、時間があるなら少しお茶でもしない?」
レティシアが言い、オルーカは快くうなずいた。
「もちろん。せっかくですからあちらで」
オルーカがテーブル席を示し、ミリーに一礼して二人でテーブル席に移動する。
「このお店って静かで雰囲気がいいし、何を注文しても美味しいから、ヴィーダにいる時はよく寄るのよ。マスターがイケメンだから目の保養になるし」
「わかります!お茶もお菓子もフードも美味しいですしね」
身を乗り出して同意するオルーカ。
そこに、マスターが水とおしぼりを持ってやってきた。
「やーなんだか嬉しくなっちゃうなー。二人ともご注文は何にするー?」
「私はダージリンでお願いします」
「じゃあ私は…えっと、ミルクティーで」
「はいかしこまりー。ミルクティーと……なんかお菓子食べる?」
レティシアはいつもはなにがしかのスイーツを一緒に頼むのでマスターがそう聞くと、彼女は苦笑して首を振った。
「今日は飲み物だけでお願い。朝ごはん食べたばかりで、まだお腹減ってないの~」
もちろん、朝食はほとんど喉を通らなかったのだが。そう言ってごまかす。
マスターは少しレティシアを見つめてから、にこりと微笑んだ。
「ダージリンとミルクティーね、かしこまりー。ちょっと待っててね」
言って、カウンターへと引き返す。
レティシアは改めてしみじみとオルーカに言った。
「こうやって会うのも久しぶりよねぇ。そもそも私たちが会う時って依頼中だから、あんまりのんびり話をしてる場合じゃない事の方が多いもんね」
「そうですね…ここでお会いする時も、何故かのんびりしていられないことが多いですし」
「そういえば、確かに」
クスリと笑ったところに、マスターが飲み物を持ってやってくる。
「はーい、ダージリンとミルクティーねー」
「ありがとうございます」
「ありがとう、マスター」
「そういえばオルーカちゃん、昨日の話受けるの?」
「えっ」
マスターの唐突な問いに、驚いて顔を上げるオルーカ。
「昨日、司祭様と話してたでしょ。故郷に帰らないかって。オルーカちゃんがいなくなると寂しくなっちゃうなーと思ってさ」
「あ……あの、ありがとうございます…」
オルーカはどう言っていいかわからずにピントのズレた受け答えをし、それから苦笑した。
「まだ…迷っていて。いいお話ではあると思うんですけど…」
「そうなんだね。寂しくなっちゃうけど、オルーカちゃんが後悔しないようによく考えるといいと思うよ」
「はい……」
マスターとオルーカのそのやり取りを、レティシアは驚いた表情のまま聞き、それから息をついた。
「そっかー…偶然ってあるのね」
レティシアの言葉に、マスターとオルーカの目が彼女を向く。
「私も実は実家に帰らなきゃいけなくなったの」
「え、そうなんですか」
驚いた様子で、オルーカ。
「えーレティシアちゃんもいなくなっちゃうのかー。綺麗どころがどんどんいなくっちゃうなー」
「き、綺麗どころだなんてそんな、オルーカはともかく…」
レティシアは恐縮して言う。
「マスター、少し茶葉を探したいのですが」
そこにカウンターから執事が声をかけ、マスターはごゆっくり、と言い残すと足早にカウンターへ戻っていった。
再びレティシアと二人になったところで、オルーカが先ほどの話を続ける。
「レティシアさんはどうして実家の方へ?」
「実は…兄ちゃんの具合が思わしくなくて…」
「お兄さん、ですか?」
「うん……私、兄が二人いてね。上の兄は元気にやってるんだけど、下の兄が昔から病気がちで……いよいよ、もう残り時間もないって言われたみたいで…」
「そうなんですね……それは、早く帰ってあげてください」
同情した様子で、オルーカ。
レティシアは苦笑した。
「うん、そのつもり。多分、冒険者も引退すると思うんだけど、その先私は何をしたらいいのか考えちゃって…」
頬杖をついて、ため息をつく。
うーん、とオルーカも眉を寄せた。
「お兄さんの調子が思わしくないのなら、旅暮らしを続けるのは難しそうですね……というか、ミケさんはどうするんですか?」
「そうなのよねー」
頬杖を通り越して、べったりとテーブルに顎をつけて。
「冒険者をやめるってことは、もうミケに会えなくなっちゃうって事になるのかなぁ。手紙は出せるんだから、何か理由をつけて会って欲しいって言ったら、ミケは優しいから会ってくれるかな?」
「ミケさんなら会ってくれそうですけど……離れ離れになっちゃうのはちょっと辛いですよね……」
オルーカも何か思うところがあるのか、視線を落としてそうつぶやく。
「オルーカもそういう人がいるの?」
「えっと、ええ…まあ、はい」
「そうなんだ。詳しく聞きたいところだけど……でも、故郷に帰っちゃったら、その人とも会えなくなっちゃう、よね…?」
「そう…なりますね」
「いいお話…ってさっき言ってたけど、帰らなくちゃいけない理由があるの?」
「故郷の教会を立て直すので、私に故郷に帰って司祭にならないかという話が持ち上がってるんです」
「司祭様に?すごい!」
純粋に感心したように、レティシア。
オルーカは苦笑した。
「でしょう?だから、いいお話、なんです。でも……」
「…帰ったら、恋人とは離れ離れになっちゃう……か」
レティシアの言葉に、オルーカは言葉なく頷き返す。
「…というか、私のことはいいんですよ。レティシアさんは、ミケさんに告白しないんですか?」
「うぇっ」
唐突というか、ある意味予定調和のオルーカの質問に、レティシアは素っ頓狂な声を上げる。
オルーカはテーブルの上にこぶしを置いて力説した。
「私も、よく考えますけど……レティシアさんも、よく考えてください。手紙が届いているうちはいいですけど…ミケさんだって、いつ私みたいに、いい話のお声がかかって、どこか知らないところに行っちゃうかもしれないんですよ!」
「そっ……そうか…ミケは優秀な魔術師だから…」
レティシアは眉を寄せて、それからオルーカと同じようにテーブルの上で手を握った。
「…うん、そうね。告白しないで帰ってしまったら、きっと後悔するよね。後になって『あの時告白していれば』ってモヤモヤするより、ダメでも言っちゃってスッキリとした方が前に進む時に後悔しないよね」
「そうですよ。やらずに後悔するよりも、やって後悔した方がずっといいです」
「うん、ありがとうオルーカ。私頑張る。オルーカも頑張ってね」
「う……はい、私も頑張りますね」
コイバナの末に笑顔を交わす女性二人。
レティシアは残りのミルクティーを飲み干すと、幾分すっきりした表情で立ち上がった。
「じゃあオルーカ、またいつか会いましょうね。あ、お手紙書きたいから連絡先教えて?」
「あっはい、とりあえずは今の教会の方に……」
言って、連絡先をさらさらと書いて渡すオルーカ。
レティシアは嬉しそうにそれを受け取った。
「ありがとうオルーカ。オルーカの方も上手くいくように祈ってるね!」
「ありがとうございます、レティシアさんもお気をつけて」
オルーカにもう一度手を振り、レティシアはカウンターへと駆け寄った。
「マスター、ごちそうさま。今までありがとう」
「行っちゃうんだねー、寂しくなるなあ」
「ヴィーダに来た時にはまた来るね。ミニウムもまたね!」
「あいー、またなのです!」
二人に挨拶をしてから、レティシアは店を出た。
来た時より、だいぶ足取りは軽くなっていた。
憧れのひとと、歌が導く行く末
「後悔しないように、かぁ……」
ハーフムーンを出てから、レティシアは継承祭で賑わう街の方に足を向けつつ、先ほどの話を反芻していた。
「ミケのことはひとまず横に置いておくにしても……家に帰った後のことだって、後悔しないようにちゃんと考えなくちゃだめだよね…」
先ほどオルーカと話したことで、ルティアが長くないと知らせを受けた時のショックはだいぶ抜け、クリアな頭で先のことを考えられるようになっていた。
ルティアのそばにいることは確定事項として、冒険者を辞めて何をして食べていくのか、具体的に考えていかなければならない。
「家に帰った後、家の手伝いをずっと続けることもできるけど、せっかく冒険者として色々経験したんだからそれを生かしたいよね……
でも…正直ずっと家にいたとして、ブランクがある状態で冒険者を再開できる自信がないなぁ。もちろん家にいたって勉強できるし、するけど、実技のカンが戻るのには時間が掛かるだろうし、まだ今は若いけど年だって取るし……生涯現役って考え方もいいけどいつか無理が来るだろうし…」
先の先のことまで考えると、また気鬱になってくる。
「憧れだけで突っ走ってきたけど、一度立ち止まってよく考える必要があるのかもしれないなー……」
などとぼやいていると。
「レティー!!」
突然名を呼ばれ、驚いて振り返る。
継承祭で人がごった返す中、向こうの方で手を振る人影が見えた。
人ごみをどうにかかき分け、レティシアの方までやってくる。
その姿に、目を丸くした。
「ルシェ姉ちゃん?!」
ようやっと目の前に来て、ほっとしたように息をついたのは。
レティシアの幼馴染であり、憧れの冒険者でもある、アルシェリア=メル=フェルシアスだった。
「久しぶり!!ヴィーダに帰って来ていたの?」
「ああ。ちょうど依頼を終えて、今は自由行動中。歩いてたら、あんたのその派手なリボンが見えたからさ、レティに間違いないと思って声掛けたんだ」
嬉しそうな表情で飛びつくレティシアに、ルシェは豪快な笑みを返す。
レティシアは、ルシェのこの快活な少年のような笑顔が大好きだった。マヒンダを出て冒険者になったのも、ルシェに憧れて、という部分が多くを占めている。
今でも彼女は、レティシアの憧れであり、大きな目標だった。
「奇遇ね。ちょうどルシェ姉ちゃんの事考えてたのよ」
「私の事?」
「そう。ルシェ姉ちゃんみたいになりたいって家を飛び出してだいぶ経つけど、その先の人生のヴィジョンというか、もっとやりたい事ってないのかなーって」
と、そこまで言ってから、レティシアはその考えに至るまでのいきさつを思い出し、慌ててルシェの服の裾を掴んだ。
「そうだ!!ちょうどココで会えたから、ルシェ姉ちゃんにも伝えておくね」
「うん?」
首をかしげて続きを促すルシェに、レティシアは深刻な表情で続ける。
「…あのね、ルティア兄ちゃんが…もう…長くないって…」
びくり、と、袖をつかんでいたルシェの手が震えるのが分かった。
さらにつづけるレティシア。
「ただ、今すぐにどうこう、ってワケじゃないって。でも、もう…ルティア兄ちゃんの身体は限界だって…」
「…そう……なんだね」
言葉少なにそう返すルシェ。
レティシアはゆっくりと頷いた。
「でね、私、マヒンダに帰ってルティア兄ちゃんの傍に居る事にしたの」
「そうか……」
ルシェは目を閉じて押し黙った。ルシェにとっても、レティシア同様、ルティアとは長い付き合いだ。もう先が長くない、と知れば、思うことも多々あるだろう。
しばらくして、ルシェは真剣な表情のまま、目を開けて頷いた。
「…わかった。私もレティと一緒に、一度マヒンダに戻ってルティアに会いに行くよ。レティはいつ発つの?」
「今日はまだ気持ちが落ち着いていないし、宿を引き払う手続きもしなきゃならないから…明後日の朝一番に出発する船かな」
「明後日かぁ…仲間にしばらく抜けるって話を通さなきゃいけないから、間に合いそうだったらレティと同じ船に乗るよ。時間が合わなくても、マヒンダには必ず戻るから」
「そうなんだね」
「ちょうど継承祭のイベントに行くって、仲間と別行動になっちゃったから、夜にでも話をするよ」
「うん。ありがとう…。じゃあ、間に合ったら明後日会いましょう」
「わかった。レティも……あんまり考えこみすぎないで」
「うん……ありがと」
自分もつらいだろうに、レティシアの顔を心配そうにのぞき込むルシェに、精一杯の笑顔を返すレティシア。
二人はそのまま、短く別れの言葉を交わし、元進んでいた方へと歩いて行った。
中央広場に近づくと、軽快な音楽が流れてくる。
「これって……どこかで聞いたような」
誘われるようにそちらに歩いていくと、音楽はどんどん大きくなってきた。
そして、中央公園の特設ステージが見えてくる。
「あっ……」
恋は メタモル☆マジック 女のコは誰でも
きっと メタモル☆マジック 恋でキレイになるの
だから メタモル☆マジック どうか魔法をかけて
いつか メタモル☆マジック 結ばれる日のために
「歌ってたの、ミューだったんだ…!」
ステージの中心でスポットライトを浴びて歌っていたのは、以前の依頼でかかわったことのあるアイドルの少女、ミュールレイン・ティカ。
もっとも、アイドルとは仮の姿で、彼女はその呪歌の才を買われてマヒンダの王宮付研究室で呪歌の研究をしている研究員なのだ。
「そういえば…ハーフムーンのマスターは熱狂的なミューのファンなのにお店に居たけど…いいのかな?」
と思いつつも、今から引き返しても間に合うとも思えず、レティシアはそのままその場でミューの歌を聴き続ける。
「はー……ミューは相変わらず歌が上手いわねぇ……」
歌声に魔力が乗っていることは理解したうえで、それでも純粋にその上手さに聞き惚れるレティシア。
少し高揚した気分になっているのは、彼女が歌に乗せた魔力のせいだろうか。
先ほどまで欝々とした気分だったのが嘘のようだ。
「人を楽しくさせる…呪歌、かぁ……」
呟いてから、はっとする。
「……これだ……!」
ミューのステージが終わってから、レティシアはステージの横から舞台裏に続く通路に来ていた。
野外特設会場だからか、目立った検閲は無い。が、スタッフと思われる人々が忙しげに動き回っており、レティシアはかなり場違いに見えた。
が、めげずに何かをきょろきょろと探しながら、レティシアは奥へと足を進めていく。
やがて。
「見つけた!ベータ!!!!!!」
大声でそう叫ぶレティシアに、呼ばれた本人はもちろん、あたりを行きかっていたスタッフが一斉にレティシアの方を向いた。
すわ不審者か、という視線を、呼ばれた本人が慌ててなだめる。
「あ、あの……えっと、僕の、し、知り合いです……」
なんだそうなの、人騒がせな、という声が飛び交い、スタッフは元通りに忙しく行き交い始めた。
ほっと胸をなでおろすベータのもとに、足早に駆けつけるレティシア。
「ああ!!良かった気が付いてくれて。大声で呼んじゃってごめんね」
「い、いえ……レティシアさん、お久しぶりです……」
ベータ、と呼んだ彼は、やはりマヒンダの王宮付研究室でゴーレムの研究をしている、ベトリクス・アムラムという青年だった。おどおどした挙動不審な様子は相変わらずだが、こんな感じでもなんとミューとは恋人同士なのである。
「お久しぶりねベータ。ミューの歌声に惹きつけられてここに立ち寄ってずっと聴いてたの」
「そ、そうなんですね……ありがとうございます…」
「相変わらずミューはカワイイわね。その後仲良くやってる?」
「あ、はい、その、おかげ、さまで……」
言葉少なに言って頬を染めるベータ。
ああ、恋人っていいなあ、とトリップしかけた頭を無理やり呼び戻して、レティシアは本題に入った。
「あのね、お願いがあるの」
「お、お願い……ですか?僕に……?」
「ベータじゃなきゃできないことなの!だからベータを探してたの!」
「は、はあ……」
「忙しいのは百も承知、私が非常識なのもよくわかってる、でもこれを逃したらもうチャンスはないから……お願い!」
がし、とベータの両腕をつかんで。
「ミューに会わせて!!」
こんこん。
「ミュー……入ります」
「ベータ?どうぞー」
ドアをノックしてベータが言うと、中からミューのものであるらしき声が返ってくる。
ベータはドアを開けると、中のミューに声をかけた。
「ミュー、お客様……です」
「お客様?あたしに?」
部屋の奥、ドレッサーの前にいたミューは、ベータの声に振り返り…そして、彼の隣にいたレティシアに気づいた。
「…あれ、あなた……えーと、前に確かベータと一緒だった……」
「レティシアよ。お久しぶり、ミュー」
「お久しぶり。その節はどーも」
ミューはステージ上のアイドルらしい甘い感じとは異なるさっぱりとした口調で、にこりと微笑んでそう返した。
以前にミューと出会った時には、レティシアはベータが『かっこよくなる』ためのお手伝いをしていて…それからなんだかんだあって、誘拐されたミューを救出するということになっていたのだった。もともとミューを護衛するために雇われた冒険者たちと違い、レティシアはベータが連れてきた知り合いというポジションだったので、冒険者ほど強烈には記憶に残っていないのだろう。
「ステージお疲れ様。相変わらず素敵な歌とパフォーマンスだったね」
「そう?そう言ってもらえると嬉しいな。演出は室長任せだけど」
レティシアはベータに促され、ミューの向かい側の丸椅子に座ると、真剣な表情でミューに向かい合った。
「あのストーカー事件の後、ミューからちょっとだけ呪歌について教えてもらったでしょ?」
「そうだったわね。あまりちゃんと教えられなかったけど」
「あの後、一人で勉強してるんだけど…どうしても独学じゃ限界があって…教わったけど使いこなせないの」
「そうねえ、技術的なところが大きいから、独学だとどうしても限界があるかもね。あたしも、室長に教えてもらったところは大きいし…」
「でね、私、ワケあって冒険者を引退してマヒンダに帰る事になったから、マヒンダでじっくり呪歌について勉強したくって…」
「ホント?いいじゃない、呪歌を使う人が増えるのは嬉しいな」
レティシアの言葉に、偽りなく嬉しそうな笑顔を見せるミュー。
レティシアは一瞬迷ったように視線をそらし、しかしもう一度彼女に目を合わせた。
「大それた夢なのはわかってるんだけど、王宮の研究室に入るにはどうしたらいいのか教えて欲しいの」
「研究室に?」
驚いたように、ミュー。
レティシアは頷いて続けた。
「ミューの歌はみんなに元気を与えてくれるでしょ?
私もその力をちゃんと理解して、使いこなせるようになって、いずれは心が傷ついた人を癒す事ができるようになりたいの」
「心が傷ついた人を癒す……」
考えもしなかった、というように、ミューはレティシアの言葉を繰り返す。
レティシアは頷いて、さらに続けた。
「呪歌は、人の心に影響するものでしょ?楽しませたり、落ち込ませたり、言うことを聞かせたり……なら、心の傷を癒すこともできるんじゃないか、って思ったの」
「確かに…理論上は可能だと思うわ。あたしも室長も、あまり考えてこなかったアプローチだけど……面白そう」
少しわくわくした様子で、ミュー。
レティシアはさらに身を乗り出した。
「そういう勉強をしていって…いずれは王宮付研究室に行きたいって思ってるんだけど……私、王宮付研究室にいる人たちがすごいってことは知ってるけど、どうやって入るのか知らなくて……ミューはどうやって研究室に入ったの?」
「うーん、あたしはスカウトで入ったのよね」
「す、スカウト」
「そう。リゼスティアルで歌ってたあたしを室長が見つけて、マヒンダに来ないかって。だから、参考にならないかも……ベータは何か知ってる?」
「え、ええと」
急に話を振られておたおたするベータ。
「あの……推薦があって試験を受けられるようになってます……」
「推薦?」
レティシアがそちらに問うと、ベータはゆっくりと頷いた。
「魔道学校か……魔術師ギルドからの推薦があって、その分野に関する試験を受けて……それで合格すれば、王宮付の研究室に入室が可能になります。
僕は……魔道学校から推薦されたので……」
「そうなんだ。んー、私は学校はもう卒業しちゃってるからなあ」
眉を寄せて、レティシア。
あの頃は冒険者になることで頭がいっぱいだったので、それ以外のギルドや推薦などの進路については一切調べなかったのだ。
「ギルドからの推薦っていうのは、具体的にはどういう風にもらえるものなのかな?」
「僕もそこまで詳しくはないですけど……他のメンバーだと、研究内容の論文が認められて推薦……というものと……ギルドの依頼などを受けて大きく貢献した功績で推薦……というケースがあったと記憶しています…」
「そうなのね。論文……はひっくり返っても無理そうだなあ……冒険者の経験を生かして、依頼を受けて貢献……っていうのがいいのかな」
むう、と悩むレティシア。
「帰ったらしばらくは家にいるつもりだし…とりあえず勉強だけは欠かさないようにしなくちゃね…」
「ごめんね、あたしの話が参考にならなくて」
苦笑して言うミューに、レティシアは大きく首を振った。
「とんでもない!すごく参考になったわ、ありがとう!ものすっごく大変で長い道のりだけど…でも、夢に手が届くように頑張る」
「うん。いつか一緒に研究できるといいわね」
「うん、ホントに!いつか研究所で会えるといいなぁ…」
「そうなれるように、頑張ってね」
「ありがとう。忙しいのに時間取らせちゃってごめんね。お二人とも仲良くって安心したわ。じゃあね」
「じゃあね」
仲良くって、の言葉に少し頬を染めて、ミューは笑顔でレティシアを見送った。
「ベータ…無茶なお願い聞いてくれてありがとう」
控室からスタッフ出口までの道のりを案内するベータに、レティシアは少し申し訳なさそうに言う。
「いえ……ミューもステージ終わっていましたし、僕の出番はもう少し後なので……」
「えっ、ベータも何かやるの?」
「あの……ゴーレムの集団行動デモンストレーションを……」
「なにそれすごい!ちょっと見てみたいなぁ…!」
「レプスの刻くらいにやるので…タイミングが合えば……」
「うん、それくらいの時間に来られたら行くね」
にこり、と笑って。
「ベータのおかげでミューに会えて、私の目指すものへの道筋が見えて嬉しかった」
「マヒンダに……戻られるんですね」
「そうなの、事情があって……だから、しばらく行動を起こすのは無理かもしれないけれど、でも、絶対研究室で勉強できるように頑張るから。
ベータとも、研究室で会えるといいね」
「はい……お会いできるのを……楽しみにしています……」
はにかんだ様子で同意するベータ。
レティシアはさらに笑みを深めた。
「その頃には、もうミューと結婚してたりしてね。そうだったら素敵よね」
「えっ……あの……その、そ、それは……」
途端に真っ赤になって慌てだすベータに別れを告げ、レティシアは特設ステージを後にした。
「はぁー幸せそうでいいなあ。私もいつかはミケと……」
ふわふわと妄想に入りかけた思考を、急に現実が引き戻す。
「そうだ。私はマヒンダに帰るんだ…。
今までみたいに、ミケと依頼で会ったりする事ってもうないんだ…」
しゅんと肩を落とすレティシア。
「ミケは素敵な人だから、ぼんやりしてたら恋人とかできちゃうかもしれない。
いつもハッキリ自分の気持ちを伝えないでいたから、ミケに気が付いてもらえなかったし、告白してフラれちゃったら元の関係には戻れないかもって怖かったから逃げてたけど…」
ハーフムーンでのオルーカの言葉を反芻する。
「今度はちゃんと言わなきゃ……!ダメならダメで、ココロの傷は大きいと思うけれど気持ちの整理はつくし。
ミケも…色々抱えている物があるみたいだから、私の事なんて考えてる余裕はないかもしれないし…逆に告白を受け入れてもらえたなら、こんな幸せな事はないし…!」
よし、とこぶしを握り締めて、改めて気合を入れるレティシア。
もうかなり歩いてきてしまったが、特設ステージの方からは再び軽快な音楽が流れてきた。子供たちの合唱のような声が聞こえる。魔道学校の生徒だろうか。
「いいなあ、私ももう一度学生に戻りたいなぁ……そうしたら推薦だって……いやいや、そこからマヒンダに残ってたらミケに会えなかったかもしれないんだから……!」
ぶんぶんと頭を振りながら、それでもマヒンダの学校での思い出に心を馳せる。
そこで、ふっとある人が頭をよぎり、レティシアは足を止めた。
「魔道学校と言えば……」
しゃらり、と、彼女の腕に着けられたブレスレットが音を立てた。
思いもよらない告白と、「友人」との別れ
「ごめんねルキシュ。待たせちゃったかな?」
フェアルーフ王立魔導士養成学校。
校門のところに立っていた青年に呼びかけながら、レティシアは急いで彼のもとに走ってきた。
「…別に。連絡があってからそれほど時間たっていないでしょ。無理して走ってくることないのに」
そっけなく言う彼は、この学校に在籍する生徒、ルキシュクリース・サー・マスターグロング。
初めは依頼人と冒険者、という立場だったが、紆余曲折あって今はそこそこ連絡を取る友人となっている。
レティシアは彼の前で足を止めると、胸を押さえて息を整えた。
「私が呼んだんだから、待たせちゃったら失礼でしょ?でもよかった、時間が取れて」
にこり、と笑いかけると、ルキシュは少し言葉に詰まって、それからふいっと目をそらした。
「…いきなり連絡してくるから、何かと思ったよ」
「ルキシュも継承祭行ってるかなとも思ったんだけど、学校にいてよかったわ」
「あまり興味は無くてね。誘われたら行ってもいいとは思ったけれど」
その「誘われたら」には「君に」が付くのだろうが、もちろんレティシアは気づかない。
「で、いきなり会いたいなんて、何の用?」
「それが……ちょっと大事な話だから、できれば人が少ない場所で話をしたいんだけど、どこかいい場所ある?」
「え」
思ったより神妙なレティシアの様子に、ルキシュは一瞬言葉を止め、それから校内の方に視線を移した。
「それなら……カフェがいいかな。いつもはそこそこ人がいるけど、今日は祭りだからほとんどいないんだよ」
「そうなんだ、じゃあカフェにしよう」
レティシアは頷いて、先導するルキシュの後に続いた。
横を歩きながら、改めて綺麗な男性だとしみじみ思う。
ルキシュはマヒンダでも指折りの名家マスターグロングの長子で、容姿が整っているのは名家とは関係なかろうが、身につけるものもしぐさも言葉遣いも貴族らしい洗練されたものだ。
しかし家からは冷遇され、マヒンダの学校でなくフェアルーフの学校に入れられた、という過去からか、かなり鬱屈した感情を内に秘めていたようで、ウォークラリーの参加者として雇われた当初はそれはそれはひどい上から目線の態度だった。
ウォークラリーの中でレティシアの判断の甘さからルキシュに大怪我を負わせてしまい、相当ぎくしゃくもしたが…結果的にはそれがきっかけで二人の関係は劇的に改善し、最終的にはウォークラリーも優勝、商品である「天の賢者様のブレスレット」を獲得したのだった。
対になっているそのブレスレットは、もう片方を持つものといつでも通信ができるというもので、レティシアは先ほどそれを使ってルキシュに連絡を取ったのだ。
ウォークラリーが終わってからも、二人はそこそこの頻度で連絡を取り合い、他愛のない話から会う約束を取り付けたり、あるいは先ほどミリーに言ったような無料の魔道講習の情報をくれたりとやり取りをしている。講習の際には成績優秀なはずのルキシュも何故か一緒に参加し、レティシアが分からないところを説明していたりもした。
そんなこんなで、友情という以上の恩義を感じている相手、なのである。
「ビックリするくらい人がいないわね」
カフェに到着すると、その言葉の通りカフェにはほとんど人がいなかった。
「みんな継承祭に出てるんだろ。学校も休みだしね」
「ルキシュはお祭りへ行かなくて良かったの?私、今ちょっと中央公園へ寄ってきたけど楽しかったわよ」
「さっきも言ったけど興味はないよ」
「そう?行けば結構面白いものよ。庶民の楽しみも体験できるのは今だけなんだから楽しめばいいのに」
言いながら、レティシアは明るくて長めのいい窓際の席を示す。
「この席でいい?」
「ああ」
促されるまま、ルキシュはレティシアの正面に座った。
一息ついて、話し出す。
「急に呼び出してゴメンね。さっきも言ったけど、大事な話があって…」
そうして、先ほどルシェに話した内容と同じことを話す。
「そういう訳で、急なんだけどマヒンダに帰る事になってね、明後日ヴィーダを発つの。ヴィーダで冒険者をやるのもおしまい」
「……そう……なんだ」
ルキシュは少なからず驚いたようで、言葉を探すようにしてゆっくりと問い返した。
「それで……冒険者をやめて…戻って、何をするつもり?」
「んー…しばらくは家で勉強しながらルティア兄ちゃんの傍にいるわ」
「そう……でも、家にいて何もしないわけにはいかないんだろ?庶民はさ」
「言うわねー。まあ、その通りなんだけど」
ルキシュの辛辣な言葉に苦笑してから、レティシアは真面目な表情で身を乗り出した。
「ねぇルキシュ」
「……何、いきなり」
「ルキシュもマヒンダの人だから王宮の研究室の事は知ってるわよね?」
「王宮付研究室のこと?もちろん知ってるよ。国内の魔道技術の最高峰だからね」
「実はね…私、研究室の研究員になりたいの」
「は?」
盛大に眉を寄せるルキシュ。
「君……正気?あそこにいられるのはごく限られたエリートだけだよ?」
「もちろん、それは百も承知よ」
しかし、ルキシュの言葉にもレティシアはめげずに続けた。
「前に研究室の職員の子と知り合ってね、その時に呪歌の事を教えてもらったの。
凄いのよ!!聴いただけで元気になって、何ていうのかな…こう、力がみなぎってくる感じ?
で、呪歌で、傷ついたココロを癒す事が出来ないかって思ったの。そういう人になりたいの」
「ふうん……呪歌、か……」
「でも、その子に教えてもらったのは、時間の都合でほんとに少しだけで、全然わからない事の方が多いから、研究所で勉強したいの。
でも、それにはギルドで実績を積んで推薦状をもらって初めて、研究員になるための試験が受けられるようになるんだって。
しかもその試験がメチャクチャ難しいらしいのよ」
「そうだね…相当狭き門だとは聞いているよ」
「気が遠くなるような話だけど、頑張ろうと思ってる」
「……そう。君がそう決めたのなら…頑張るといいよ。君なら……もしかしたら、想像もしないようなことが出来るような、そんな気もするしね」
先ほどまで呆れたように否定していたルキシュだったが、レティシアの気迫に押されてか、苦笑してそう言った。
レティシアはありがとう、と嬉しそうに言い、それからため息をついた。
「きっと、マヒンダに帰っちゃったら…もうルキシュに会う事なんてできないでしょうね。寂しいなぁ。せっかく友達になったのに…」
「…そうだね」
「あ、でもこのブレスレットがあれば、お話はできるわよね。帰ってからも連絡していい?」
「もちろん。というか、僕も卒業すればマヒンダに帰るかもしれないし……」
「あっ、それもそうか。そうしたらまた、マヒンダで会えるかもしれないね」
嬉しそうにそう言ってから、また、ふう、と息をつく。
帰った後のことが具体的になるにつれ、ヴィーダを離れなければならないのだ、という現実感がわいてきて。
「ねえルキシュ。ミケの事覚えてる?ウォークラリーで対戦した彼。ああ、文化祭で一緒にお茶したこともあるから覚えてるよね?」
「……もちろん、覚えてるよ」
少し複雑そうな表情で、ルキシュ。
覚えているも何も、ウォークラリーでルキシュをボコボコにしたのは当のミケだ。
そして。
「私ね、………実はミケの事が好きなの」
「……そう」
特に驚きもなくそう返すルキシュ。
ウォークラリーの時も、ハーフムーンの時も、そして文化祭の時も。レティシアがミケに好意を寄せていることは、ルキシュにはわかりすぎるほどわかっていた。
なぜなら。
「ミケにも…もう会う機会がなくなると思うから、思い切って告白しようと思って。
気持ちが隠せない性分だから、ミケにいつかバレちゃうかと思ったんだけど、ミケったら全然気が付いてくれないんだもの…。だから、ちゃんと伝わるように想いを告げるわ」
少し不安そうに、それでも幸せそうにそんなことを言うレティシアの態度は、完全に「女友達に恋の相談をする」時のそれで。
ルキシュはイラっとしたように、眉を寄せた。
「…何度か見た感じだと、向こうにそんな気は全然なかったようだけど?気が付かないってことは望みがないってことなんじゃないの?」
「まあ…ね。望みが薄いのはわかってるけど」
レティシアは苦笑してそう答えた。
その答えに、さらにイライラしたように、ルキシュ
「マヒンダに帰ったって、向こうが冒険者ならまた会うこともあるかもしれない。けど、告白してフラれたら、気まずくなってもう会うこともできないんじゃないの」
「それもわかってるよ」
レティシアは強い口調で言い返した。
「でも、告白しないで曖昧なままミケから離れちゃったら、いつか言わなかった事を後悔すると思うの。
きっともうその時には取返しがつかなくて、ずっと「言えばよかった」って思い続ける。ココロの中に棘がささったままみたいに、チクチク痛み続ける…。
だったら、ダメで元々だと思って言っちゃった方がいいじゃない?」
「………」
沈黙が落ちる。
しばし、レティシアとルキシュの視線が沈黙の中でじっと向き合っていた。
「……そう」
なかば、挑戦的とも言える鋭い視線を向けながら、ルキシュはゆっくりと言った。
「君が…諦めない、後悔しないように、って言うなら。
僕もそれに倣うことにするよ」
言葉の意味が分からず、きょとんとするレティシアに。
ルキシュは彼女をじっと見据えたまま、言った。
「……君が好きだ」
レティシアの瞳が大きく見開かれる。
そう。
ミケを認識していたのも。レティシアがミケを好きだということに気づいたのも。すべて彼自身が同じように、レティシアに好意を寄せていたから。
向こうにそんな気は全然無い。気が付かないっていうことは望みがない。告白してフラれたら、気まずくて会うこともできなくなる。
すべて、彼自身のことだった。
「ルキシュがそんな風に思ってくれてたなんて…気が付かなかった…」
レティシアがやっと絞り出した一言に、ルキシュは皮肉気に微笑んだ。
「君はミケのことしか見ていなかったからね。同じだと思っていたよ。ずっと」
「そう……そう、か……」
レティシアはよく回らない頭で俯いて考え、しばらくして再び顔を上げた。
「…私の事を好きになってくれて…ありがとう…。でも、私の気持ちは変わらないわ」
きっぱりと。ルキシュの目を見て、そう言い切る。
「それに、ミケへの想いが叶いそうにないからって、今ルキシュの気持ちに応えたら、それはルキシュに対して失礼じゃない?
ルキシュが真剣に私の事を好きだって思ってくれたのと同じくらい、私はやっぱりミケが好き」
「……君なら、そう言うと思っていたよ」
ルキシュは、わかっていた、というように苦笑した。
レティシアは一瞬辛そうに眉を寄せて、それから笑顔で立ち上がる。
「ルキシュの気持ち、嬉しいよ。本当にありがとう。…私も頑張って、気持ち伝えてくるね」
これ以上彼の顔を見ていると泣いてしまいそうで、じゃあ、とあいさつもそこそこに踵を返す。
そして、カフェを出るべく足を踏み出した、その時。
がくん。
突然後ろから引き戻されて、レティシアの足が止まる。
ルキシュが立ち上がり、後ろから彼女を抱きしめていた。
「……っ…」
言葉が出ないレティシア。
こつん、と、後頭部に彼が額を当てた感触があった。
絞り出すような声が、頭の後ろから響く。
「…すまない。もう少しだけ」
「………」
やはり、返す言葉が思いつかない。
彼はレティシアの後ろで、表情を見せないまま、囁くように言った。
「…この僕を振るんだからね。後悔しないように、全部ぶちまけておいで。
はっきりと応援はできないけど……まあ、うまくいくといいね」
「……ありがとう」
レティシアはやんわりとルキシュの腕に手を置き、それを解いた。
「それじゃ、私…行くね」
「……ああ。気を付けて」
先ほどのように気軽に、また連絡するね、の挨拶はしなかった。
……できなかった。
カフェを出て、出口へと向かう足取りは重い。
ルキシュに出会ってから、これまでのことが次々に思い出される。
いつから、彼は自分のことをそんな風に想っていてくれたんだろう。先ほどの告白の瞬間まで、レティシアはそんな風に想われていることなど全く考えたこともなかった。
だが。
(ルキシュと私がお互いに持っている「好き」って気持ちは、言葉は同じだけど本質が違う。だから私はルキシュの気持ちには応えられない)
それは、レティシアがミケに対して抱いている不安と同じものではないか。
『同じだと思っていたよ。ずっと』
ルキシュはそう言っていた。
ミケがレティシアの想いに全く気付いてくれなかったように、ルキシュの想いもレティシアは全く気付かなかった。
レティシアが、ミケに決定的に拒絶されるのが怖くて告白が出来なかった、それと全く同じ思いを、ルキシュもしていたのだろう。
想いを寄せている相手が、目の前で別の相手への好意を語る、などと。自分なら耐えられるだろうか。
「………」
ほろり。
一度目からあふれ出した涙は、すぐに止められないほどほろほろとあふれ続け、視界を滲ませる。
歩いていた足は、いつの間にか動きを止めていた。
ぽたぽたと床に落ちる雫をどうにかぬぐいながら、レティシアはしばし、声を殺して泣いた。
初めての懐かしさと、行く末を告げる声
「あれっ、レティシアじゃない?」
魔道学校の校門で。
ようやく泣き止んで目元の晴れを気にしていたレティシアに、後ろから元気な声がかかる。
聞き覚えのある声に振り向くと、そこには。
「カイ!久しぶりね!」
この魔道学校に通う竜族の少女、カイの姿。その隣には、カイといろいろな意味で正反対の印象がある、瑠璃色の髪の少女が立っている。
「久しぶり。学校に何か用だった?」
「え、と、うん、まあ。もう用は終わったから帰るところよ」
どうにかごまかして、視線を隣の少女へと向ける。
「ところでカイ、こちらのカワイイお嬢さんはお友達?今日はマルは?一緒じゃないの?」」
「ここにいますぅ……」
弱々しい声とともに、カイの後ろからひょいと顔を覗かせるマル。
レティシアはあはは、と笑った。
「ごめんごめん、気づかなくて……それで、こちらの方は?」
「こっちはミルカだよ。あたしのルームメイト」
「初めまして、ミルカ・アレディーナよ」
カイの隣にいた少女…ミルカは、気さくな様子でそう言った。
「ミルカね。よろしく。私は、レティシア・ルードよ」
「レティシア…なら、ティッシね!よろしくね!」
速攻で今までにない愛称をつけるミルカ。レティシアは特に気にした様子もなく、話を続ける。
「私の勘違いだったらゴメンね。私、ミルカとは初対面じゃないような気がするんだけど、どこかで会った事あったっけ?」
「ううん、初対面だと思うけど……うっ……わたしの頭に何かの電波が…ブルーポスト……黒ボンデージ……ううっ、頭が!」
「ちょっ、なんか私の頭にも来そうだけど大丈夫?!」
「大丈夫大丈夫。まあほら、最初から波長が合って自然体で話せる相手っているわよね!」
「そ、そうよね…?」
不思議なやり取りをしているところに、カイが横から尋ねる。
「そういえば用事って?」
「ああ、それがね……マヒンダにある実家に帰る事になったから、知り合いに挨拶に来たの」
「えっ、レティシア帰るの?」
驚いた様子で、カイ。
「そうなの。ちょっと、家の事情でね」
苦笑して言い、あまりこの話を続けると暗くなってしまいそうだったので、レティシアはすぐに話題を変えた。
「3人はこれからどこかに行くの?」
「バザールの方に行こうと思ってたんだ。レティシアは?」
「あ……じゃあ、ご一緒していい?そっちの方に行こうと思ってたんだ」
行こうと思っていた、というのは、今とっさに口にした嘘だが。
今は、とりあえず一人になりたくなかった。
「私が冒険者として一番最初に受けた依頼が、実はカイの依頼だったのよね」
「そうなんだ?懐かしいね」
「そうだね…ロッテの事件で会ったり、パフィの事件で会ったり……マルの依頼に関わったりもしたわね」
「そ、そのせつはお世話になりましたぁ……」
「えっ、じゃあ、マルカイのキューピッドをティッシたちがやったってこと?」
興味津々にミルカが言い、レティシアは頷いた。
「そうなの。まあ私はあんまり何の役にも立ってなかったけど…」
「そ、そんなことないですよぉ……あのぉ、皆さんには本当にお世話になってぇ……」
「その後、カイとはどうなの?進展してる?」
「し、ししし、進展ですかぁ?」
真っ赤になって慌てるマル。
あ、こりゃあんまり進んでないな、と瞬時に納得した。
「マルがカイのところに来た話、なんか相当面白かったって聞いたから、ちょっとその場に居合わせたかったわ」
楽しそうに言うミルカに、レティシアが問う。
「ミルカは、カイのルームメイトなのよね?」
「そうよ」
「サバサバしたカイと、なんていうか、対照的っていうか……その服とか」
「ああ、これ?都会の魔道士学校に入学するって言ったら母が作ってくれたんだけど…田舎者の発想は何かズレてるのよねー」
苦笑して言うミルカに、レティシアはとんでもないというように手を振った。
「そんなことないわよ!すっごく似合ってる!髪の毛も…それ、どうしてるの?」
「地毛なのよー。ちょっと油断すると爆発しちゃうの。ティッシみたいなさらさらストレートがうらやましいわ」
「長いと大変よねー。おすすめのヘアケアとかある?」
「最近のお気に入りはね、スイートエンジェルっていうブランドの……」
乙女のファッション談義はバザールに到着するまで続いた。
バザールの入り口に到着すると、レティシアは3人を振り返った。
「カイたちはどっちへ行くの?」
「そうだね、あんまり決めてないけど……昨日通りがかった時に、なんかよさそうな武器売ってるところがあったから、そっちに行こうかなと思って」
そっち、と言って目的の方向を指さすカイ。
レティシアは笑顔で頷いた。
「そうなんだ。じゃあ私は反対方向だから、ここでお別れね」
反対方向、というのも微妙に嘘だ。あまり3人の邪魔をするのもはばかられたので、最初から示された方向と反対方向へ行こうと思っていた。
「また会えたら会いましょう。カイ、マル、元気でね。マヒンダに来る事があったら『蒼月の館』って食堂に来て。私の実家なの」
「蒼月の館、ね。覚えとく」
「あ、あのぉ、レティシアさんもぉ、お元気で……」
カイとマルに挨拶してから、レティシアはミルカに向き直る。
「初めましてなのに、ちっとも初めてな感じがしなかったわ」
「ふふ、わたしも」
「やっぱりどこかで会ってたのかもね」
「本当に。せっかく知り合えたのにもうお別れだなんて寂しいわね」
「そうね……ミルカもマヒンダに来たら、ぜひ実家に遊びに来て」
「ええ、必ず!」
笑顔で手を振って、ティッシはカイたちと別れて歩き出した。
「って、こっちに来たものの、特に何か買いたいものがあるわけじゃないのよねぇ……」
3人と別れ、バザールの中をぷらぷらと歩くレティシア。
「あー…兄ちゃんたちにお土産買って行こうかな。父さんと母さんには、この辺でしか手に入らないスパイスでもお土産にしよう」
家族への土産を物色すべく、さらに足を進めると。
「あれ……なんだろあの列」
向こうの方に列ができているテントを見つけ、首をかしげる。
興味津々でそちらのほうに歩いていくと、占い、という看板が目についた。
「占いかぁ…」
ここまで列ができているということは、よく当たる占い師なのだろう。レティシア自身はあまり占いに興味がある方ではないが……信じていないというよりは、いい結果が出たらそれに甘んじて努力をしなくなりそうで、あえて意識しないようにしている。
「そんなに評判の占い師なら、私も何か見てもらおうかな……」
そんなミーハー心半分で、行列の後ろに並ぼうと足を進めると。
「はい、次の方はこちらに並んでください」
テントの入り口から列整理をしていた青年がやってきて、列の最後尾を促した。
その顔を見て驚くレティシア。
「あれ……フカヤ?」
「うん?……あれ、レティシア。久しぶりだね」
言って柔らかい笑みを返したのは、以前かかわった事件の中で知り合った狼獣人の青年、フカヤ。
「っていうことは、ここはパフィの占いの館なのね?」
「うん、そうだよ」
「そういえば、あの依頼の時も良く当たるって評判だったものね」
「パフィの占いはよく当たるからね。レティシアも時間があったら占っていって?」
「うん、そうするわ」
にこりと笑みを返して最後尾に並ぶと、フカヤは再び列整理に戻っていく。
その後ろ姿を見つめながら、レティシアはフカヤと出会った事件のことを思い返していた。
その事件で、フカヤは依頼人だったわけではない。むしろ、依頼人が探していた人物の恋人として出会った青年だった。
結論として、探し人は家族の仇などではなく、その大きな力を狙った依頼人が嘘をついて冒険者たちを煽り立てていた。
大きな力を得た依頼人は、その力を持ってどんな悪行をするかわからない。力を返してもらえないのなら…最悪、命を絶つしかない、という結論になった。
冒険者として初めて、「人を殺める」という可能性に直面した依頼。
レティシアは悩み、その現実に恐怖した。その気持ちを鎮めてくれたのもまた、ミケだった。
あの時も、ミケが私を励ましてくれて、そっと手を握ってくれたら、すぅっと震えが収まった。
それで覚悟は決まったはずだったのに、いざ対峙すると、やっぱり怖くて…
呪文は唱えられたけれど、小さく震え出した私の手に気が付いて、ミケが手を添えてくれた。だから私は頑張れたんだ。
結局その事件では、依頼人を殺めることはなかったが……この事件は、彼女に大きな変化をもたらした、と今でも思う。
そんなことを考えているうちに列は進み、レティシアの番になった。
テントの入り口の幕を上げ、どうぞ、と促すフカヤに、一礼して中に入る。
「ようこそなのねー」
中で出迎えたのは、くだんの依頼で「探し人」であった少女……白竜族のパフィだった。
「こんにちは、パフィ。お久しぶり」
「レティシア!お久しぶりなのー」
レティシアがあいさつをすると、パフィは嬉しそうに微笑んでそれに応える。
レティシアは早速パフィの正面に用意された椅子に座った。
「フカヤとまだ旅をしてるのね。相変わらず仲が良くて、羨ましいわ」
「うふふー、フカヤが手伝ってくれて助かってるのー」
「私も、やっと好きな人に気持ちを伝えようって決心したの」
「そうなのー?それじゃあ、そのことについて占うのー?」
「……ううん」
レティシアは少し迷ったような表情で、それでも首を横に振った。
「本音を言えば占って欲しい。結果を知って安心したい…そんな気持ちがあるのは確かよ。
でも、私って甘ったれだから、結果を知っちゃったらがむしゃらに頑張れないような気がするから、応援だけして」
「わかったのー。がんばるのねー」
「ありがとう」
「じゃあ、何を占うのー?」
問われて、うーんと首をひねる。
「じゃあ…今日私がミケに会えるか占って。ミケの事覚えてる?私と同じ依頼で会ってるんだけど…」
「覚えてるのねー。じゃあ、占うのー」
パフィは言って、テーブルの上に積まれたカードの束に手をかざす。
ふわり。
カードが浮き上がり、その中の1枚がすいっと飛び出てテーブルに着地した。
「すごい……」
感嘆の声を上げるレティシアの前で、ゆっくりとカードをめくるパフィ。
「ミドルヴァースの正位置……願いは叶い、待ち人は来る……」
「本当?!今日会えるのね!?」
身を乗り出すレティシア。
「じゃあ、ますます頑張らなくちゃ。いつも照れくさくてちゃんと言えなかったけど、ちゃんと告白してくるわ」
「がんばるのねー」
相変わらずの温和な口調で励ますパフィ。
レティシアは占いの代金をテーブルの上に置くと、立ち上がった。
「それじゃあ、またね。ありがとう」
「ありがとうなのー」
パフィに手を振って別れを言い、テントの外にいるフカヤにも笑顔で手を振って別れた。
再度バザールに戻ったレティシアは、先ほど思った通り、家族へのお土産を物色した。
「兄ちゃん達には…このブックカバーでいいかな…」
雑貨屋でよさそうなブックカバーを選んでいると、横から伸びてきた手とぶつかってしまう。
「あっ、ごめんなさい」
「ううん、こっちこそゴメ……って、レティシア?」
「えっ」
名を呼ばれて、顔を見れば。
「ロッテ!お久しぶり!それにリーも」
以前の依頼で旅を共にしたロッテと、依頼人であるリーの姿があった。
リーもレティシアの顔を見ると、嬉しそうに表情をほころばせる。
「お久しぶり。元気そうでよかったわ」
「レティシアは何を探してたのん?」
「えっと、兄ちゃんたちへのお土産をね」
「兄ちゃんって、前に来たエリオットくん?だっけ?」
「よく覚えてるわね。エール兄ちゃんと、もう一人兄ちゃんがいるの。だから、二人に、かな」
「へー。里帰りすんの?エリオットくんと約束してたもんね?」
「ううん……里帰りじゃなくて、実家に戻ることにしたんだ」
苦笑して言うレティシアに、ロッテは少なからず驚いたようだった。
「えー!じゃあ、冒険者やめちゃうのん?」
「うん……今のところはそのつもり。いずれはいろいろ勉強して、ギルドや研究室に入りたいと思ってるけど…」
「そうなのね。じゃあ、もうヴィーダに来ても会えないし…旅先で会うようなこともなくなるのね」
寂しそうに言うリー。レティシアは苦笑した。
「うん…だけど、戻ってからも、目標に向かって頑張るから!そうだ、マヒンダに来る事があったら『蒼月の館』って食堂に来て。私の実家なの」
「ええ、是非寄らせてもらうわね」
「そーいや、ミケは?」
きょろきょろとあたりを見回すロッテ。レティシアはきょとんとしてそちらを見た。
「え?別にミケと一緒に行動はしてないけど……」
「えー、そーなん?さっきミシェルちゃんのところで見たからさあ、てっきり一緒なんだと思ってたけど」
「ミケを見たの?!」
驚きに声を上げてから、レティシアは嬉しそうに手を合わせた。
「パフィの占い通り、ミケに会える予感…!ありがとうロッテ!お祭り楽しんでね!じゃあね!」
せわしなく手を振ると、レティシアは早速ミケを探しにバザールへと繰り出すのだった。
ライバルとの対面と、恋の決着
「うーんん……やっぱりいなかったなぁ…今日会えるんじゃないのかなぁ…」
しばらくバザールをうろうろしていたが、結局ミケには会えず。
そのまままた中央広場まで来て、ベータのゴーレムショーを見て。
レティシアは会場を出ると、またぶらぶらと歩き始めた。
すると、会場の裏手の方で、どぉんと大きな音がする。
「何……爆発?」
いぶかしげな表情で、そちらの方へと足を向けると。
正面から、見覚えのある姿がやってきた。
長い亜麻色の髪、桜色の異国風の装束。整った顔立ちに上品な立ち居振る舞い。
「え…?リリィ…?」
レティシアのライバルである、リリィの姿がそこにあった。
硬直して足を止めるレティシア。
彼女はレティシアに気づくと、にこりと微笑んでこちらにやってきた。
「レティシアさんじゃないですか。お久しぶりです」
「わ…私に何か用?今日は私、ミケと一緒じゃないわよ」
警戒した様子でそう返すと、リリィはあっさりした様子で答えた。
「え?知ってますよ。さっきまで一緒にいましたから」
「え、一緒に…?!」
がつん、と殴られたような衝撃。
しばし言葉に詰まってから、レティシアはおそるおそるリリィに訊いた。
「どこで…会ったの?」
彼女の様子を、リリィはじっと見て……それから、おもむろにスッと目を細めた。
「内緒です。私とミケさんの」
面白そうに言うリリィ。
レティシアはきっと彼女をにらみつけた。
「ミケに…会いたいの。ミケに会って、言いたい事があるの」
「言いたいこと、ですか?もしかして告白とか?きゃっ」
「……っ………」
「あらあら、図星ですか」
可笑しそうに笑うリリィ。
「…何が、おかしいの?私がミケに告白しちゃいけない?」
「えーでもミケさん、あれだけレティシアさんが好き好きアピールしてるのに全然気づかないじゃないですかー。もう駄目なんじゃないです?あの人恋愛アンテナ死んでるんですよ」
本人がいないのをいいことに(いても同じことを言っただろうが)言いたい放題である。
レティシアは少し逡巡した様子で、視線を泳がせた。
「……でも、後悔したくないの。もう会えなくなるなら…望みが薄くたって、最後まで諦めたくない……」
「後悔したくない、のは、レティシアさんのためですよね?」
ゆっくりと。
リリィは、俯くレティシアのそばにかがんで、耳元でそう言った。
「後悔したくなくて、諦めたくなくて。一方的な思いをぶつけて、レティシアさんはそれで満足なんですね?
何とも思っていなかった相手から、突然好意をぶつけられて。親しい友人だと思っていたのに、断ることで気まずくなってそれからずっと疎遠になる…なんて。
一方的にそんなことされた側の気持ちって、考えたことあります?」
「っ………」
リリィの言葉は、レティシアの胸をこれ以上なく正確に抉った。
まさに、自分がルキシュに対して、先ほど経験してきたものだったから。
くすり。
リリィは楽しげに鼻を鳴らすと、さらに続けた。
「告白するのが勇気か、しないのが英断か……決めるのは誰でしょうね?
想いを伝えるなんて、所詮は自分のエゴ……それを理解した方がいいと思いますよ?」
呆然とした様子で、言葉も出ないレティシア。
リリィはそれを見て満足そうに微笑むと、顔を上げて歩き出した。
「では、私は今度こそチャカ様のもとに戻りますね。ごきげんよう」
リリィが去った後も、レティシアはしばらくそこを動けずにいた。
先ほどようやく引っ込んだ涙が、またほろほろとこぼれてくる。今日だけで何回泣いただろうか、もう自分でも覚えていない。
『後悔したくない、のは、レティシアさんのためですよね?』
『一方的にそんなことされた側の気持ちって、考えたことあります?』
『想いを伝えるなんて、所詮は自分のエゴ……それを理解した方がいいと思いますよ?』
リリィの言葉が頭の中をこだまする。
やっぱり無謀なのかな?
ミケみたいな素敵な人には、私は相応しくないのかな?
告白なんて…しない方がいいのかな…?
ふらふらと。
レティシアは無意識に歩き出した。
自分でもどこに向かっているのかはわからなかった。
街の喧騒が遠ざかっていく。
日もだいぶ暮れてきた。もうすぐ夜になるだろう。
とぼとぼと歩いてきたレティシアは、ふと、見覚えのある景色に意識を引き戻された。
「真昼の月亭……」
そこは、レティシアが冒険者になって初めて依頼を受けた酒場であり……ミケと初めて会った場所だった。
冒険者として初めての依頼で緊張していた私が、それを忘れてしまうくらい、ミケに一目惚れしたのはココでの事だったっけ。
それからずっとずっと、ミケの事が好きで。
依頼を受けるたび、今回はミケが一緒だといいな、ってドキドキして。
一緒の依頼を受けられた時は片時も離れたくなくて、ミケと行動する事が多かったなぁ。
気弱になっている時はいつだって、優しく、時には厳しく、私を励ましてくれたミケ。
私は一生懸命好きだって伝えてたつもりだったけど、いつも気が付いてくれない…そんな鈍い所も好き。
私の冒険者としての思い出の中には、いつもミケがいて。
思い出すのは、優しい彼の笑顔と、私を呼んでくれる穏やかな声…
かと思えば、冒険の中ではクレバーに冷静に判断を下して。魔法の腕も一流で、とても頼りになって。
一度、すごく怒ったのを見たことがあったな…少し怖かったけど、でもやっぱりカッコよくて、私のために怒ってくれたことが嬉しかった。
ミケに関わった思い出の何もかもが、胸の中に温かく蘇る。
レティシアは顔を上げて、再び真昼の月亭の看板を見上げた。
「せっかくココに来たんだったら、アカネにも挨拶していこうかな。いっぱいお世話になったし」
自分を励ますようにそう呟いて、ドアを開ける。
からん。
涼しげなドアベルの音が店内に響き、中の客の注目を引いた。
すると。
「レティシアさん…!」
中から聞こえた声に、レティシアは驚いて立ち止まった。
「うそ、ミケ…!」
ミケは立ち上がって、レティシアに笑顔を向けた。
「こんばんは、レティシアさん。お久しぶりです」
「……っ」
ミケの笑顔に喉が詰まったように言葉を返せず、レティシアは小さくつぶやいた。
「うそ…パフィの占い…本当に当たるのね…」
それから、うん、と小さくうなずいて、ミケがいる席のところまで歩いていく。
「こんばんは、ミケ。ご一緒してもいい?」
「はい、もちろんです。どうぞ」
ミケは笑顔で自分の席の正面を促した。
レティシアは頷いて、その席に腰を下ろす。
そこに、アカネが水とメニューを持ってやってきた。
「レティシアさん、いらっしゃいませ!……あれっ、大丈夫ですか?」
レティシアの目元が赤いのを心配そうにレティシアをのぞき込むアカネ。
レティシアは苦笑して首を振った。
「大丈夫よ。ありがとう、ごめんね、心配かけて。私はレモンスカッシュでお願い」
「あっ、はい。かしこまりましたー」
アカネは水を置いてそのままカウンターへ戻っていき、割とすぐにレモンスカッシュを持ってきた。
レティシアはぎこちなくそれを受け取ると、ミケの方を見ずに、そのまま視線を落とした。
「レティシアさん……」
ミケが話しかけようとしたところで、レティシアは思い切ったように顔を上げた。
「あのねっ」
真っ赤な目元で、何かを言いよどむように言葉を切って。
それから、ゆっくりと話し始める。
「ミケに会えて良かったわ。大事な話があったの」
「大事な話…ですか」
神妙な表情に、ミケも顔を引き締めて対する。
レティシアは頷いて続けた。
「実はね、私…マヒンダに帰る事になったの」
「えっ」
「ルティア兄ちゃんの事覚えてる?ルティア兄ちゃんがね…もう長くないってお医者さんに言われちゃって…」
そこで、感極まったように言葉を詰まらせる。
「でね、残りの時間を家族で過ごそうっていう事になったから、明後日帰る事にしたの。ヴィーダでの冒険者としてのお仕事は店じまい」
「そう…なんですね」
「で、マヒンダに帰ったら、ミューのいる王立研究所の研究員になるためにギルドで勉強して、研究員になるための試験を受けられるように頑張ろうと思って」
「えっ、王立研究所って……結構ハードルが高いって、聞いたことありますけど」
「そうなの。でも、ミューの呪歌を聴いて、呪歌で人のココロを癒す事ができるようになれたらいいなーって思ってね」
「ああ…それでミューさんが、レティシアさんが来たって言ってたんですね」
「ミューから聞いたの?そう、すっごくすっごく大変な道のりだよってミューにもルキシュにも言われたけど、何も頑張らないうちから諦めたくないから……頑張るわ」
「そうですか……」
ミケは少しほっとしたように息をついた。
そして、彼も俯いて話しだす。
「実は、僕も。故郷に帰るんです」
「えっ」
ミケの言葉に驚くレティシア。
ミケは続けた。
「僕の書いた研究レポートが、故郷の…ザフィルスの魔術師ギルドで評価されたようで。研究者のポストを用意するので、ギルドに来てほしいと」
「す…すごいじゃない、ミケ!さすがミケね!」
レティシアは大きく目を見開いて驚いて、それからすぐに素直に賛辞を述べた。
「じゃあ、ミケは故郷に戻って、えらい研究者さんになるんだね…」
「え、いや、まだそこまでは……とりあえず帰って、話を聞こうかなって」
「うん、すごいチャンスだし、よくお話聞いて、ミケにとってプラスになる方向になるといいね!」
降ってわいたミケの喜ばしい話に、心から嬉しそうに言うレティシア。
しかし、その肩がすぐにしぼんだ。
「そっか……ミケも地元に帰るんだ…」
「……レティシアさん…?」
肩を落としたレティシアの様子に心配そうに声をかけるミケ。
だが、レティシアはまた深い思考の中に意識を落としていた。
何となく、もうミケと二度と会えないんじゃないかって不安になった。
何でだろう。ミケはいつでも私を待っていてくれてるような、そんな風に考えていた。
今までだって、別に同じ依頼を受けようと約束して一緒にいたわけじゃないんだし、何でそんな事を考えたのか、自分でもわからない。
もちろん手紙を出せばミケに届くし、会おうと思えば会えるのかもしれない。
でも、今までみたいに…気が付けば傍に居てくれてる…なんて事はもうないんだ。
それなら…
やっぱり自分の気持ちを告げていった方がいいんじゃないのかな?
ルキシュに言ったように、今、告白しないでミケと会えなくなったら、ずっとずっと「あの時、ダメでも気持ちを伝えておけば良かった」って思い続けるだろう。
例えば私が別の人と結婚して家庭を作っていても、何年も経って年を取っても、ふとした時に思い出して胸が痛むだろう。
でも、私がルキシュの気持ちに気づかずにずっと友達だと思っていたように、ミケも私の事をただの仲間だとしか見ていなかったらどうするの?
それに…私はミケの隣に立って一緒に歩んでいけるような、そんな立派な人間だとは思えない。
『想いを伝えるなんて、所詮は自分のエゴ……それを理解した方がいいと思いますよ?』
リリィの言葉が再び蘇り、レティシアはそれを振り払うように首を振った。
悩んでいる場合ではない。
ミケはもういなくなる。自分と同じように、故郷に帰ってしまう。
一方的でも。エゴでも。
最初に決めた気持ちを大切にして、言葉にして伝えて、新しい道へ歩き出そう。
「ミケ」
「あっ、はい」
ようやく戻ってきたレティシアの呼びかけに、神妙な表情で答えるミケ。
レティシアは改めて、真昼の月亭を見回した。
「ミケは私に初めて会った時の事…覚えてる?リュウアンの…ほら、カイが依頼主だったメイの事件の…。私たち、あの時ココで初めて会ったのよね」
「そう…でしたね。懐かしいな……」
ふ、と一つ息をついて。
レティシアは改めてミケを正面から見つめなおした。
「あの時からね、私ね、ずっとミケが好き。仲間としてじゃなくて…あ!!もちろん仲間としても好きだけど、そうじゃなくて…その…あの…」
どう言っていいのか、考えあぐねるように。口をはくはくさせながら、懸命に言葉を紡ぐ。
「最初は…気を悪くしたらゴメンね、実は一目惚れで…要はミケの見た目に惹かれたの。
でも、一緒に過ごしていくうちに、ミケの聡明で真面目な所や仲間思いな所、控えめそうなのに、リーダーシップを取ってみんなを纏めるしっかりした一面も知って、もっともっと好きになった…」
幸せそうに、しかし時折苦しそうに胸を押さえながら。
一呼吸おいて、もう一度。
まっすぐにミケを見つめて、レティシアはゆっくりと言った。
「私は、ミケが好き」
沈黙が落ちる。
レティシアはミケの反応を、一挙手一投足を、一言一句を見逃すまいとするかのように、じっと彼を見つめている。
ミケは先ほどのレティシアと同じように、しばらく言葉もないほどに驚いた様子だったが…やがて、ゆるく微笑んで、頷いた。
「…ありがとう、ございます。まさか、自分がそんな風に想われることがあるなんて思ってなかったから、すごく驚いて……でも、純粋に嬉しいと思います」
「ミケ……」
「あなたのことは、とても素敵な人だと思っています、優しくてとても強い方で、好ましい。でも」
目を閉じて、ゆるく首を振って。
「今、僕もいっぱいいっぱいで、それに応えることはできません。ごめんなさい」
「ミケ……」
なんとなく、この返事は予想していたのかもしれない。
妙にすっきりとしたような気持ちで、レティシアは微笑んだ。
「ありがとうミケ。離れ離れになっちゃうけど、お手紙書くわ。お互い落ち着いたら、また会えるといいわね」
「ええ……是非。落ち着いたら、僕も手紙を書きます。マヒンダのギルドで頑張るなら、そちらあてに送れば届きますよね」
「うん……うん、待ってる」
これ以上話したらまた泣いてしまいそうで、レティシアはそわそわと立ち上がると、財布を取り出した。
「アカネ!早いけどごちそうさま、これ、お代ね!」
カウンターの方に行き、取り出した銀貨をアカネに渡す。
「あっ、ありがとうございます…」
「アカネ、今までありがとう。私、実家に帰るの」
「そうなんですね、寂しくなりますね…」
「…ヴィーダに来た時は…また…遊びに…来るから…」
レティシアは何かをこらえるように俯くと、パッとミケを振り返った。
まだ目元が赤い、しかし満面の笑顔で。
「じゃあね、ミケ!!またね!!」
「レティシアさん……はい、また!」
彼女の最後の挨拶に、ミケも満面の笑顔を返す。
レティシアは何かを振り切るように、足早に出口に向かった。
からん。
「っと、すみません……」
「っ、こちらこそ、ごめんなさい…!」
入ってきた男性とぶつかりそうになり、慌てて謝ると、レティシアはそのまま外へ駆けだした。
真昼の月亭のあかりが見えなくなるまで走り、そこでようやく足を止めて、空を見る。
いつの間にか日は暮れ、空には星が輝いていた。
すう、とまた涙が一つこぼれる。
後悔の涙ではない、と断言できる。が、なぜ涙がこぼれるのか、自分でもよくわからなかった。
もともと望みの薄い恋だった。ミケの返事は、どこか予感していて。その通りの返事が来たことに、妙に納得もしていた。
だから、これは恋が実らなかった悲しみの涙…ではない。はずだ。
再び宿への道を歩き出しながら、レティシアは溢れる涙を何度もぬぐう。
涙があふれるたびに、ミケとの思い出が心の中を駆け巡っていった。
「悲しいんじゃなくて…寂しい…のかな…」
自分が言ったその言葉が、妙に胸にすとんと落ちてきて。
溢れてきた思いを流しきるように、宿への道すがらも、そして宿に着いてからも、レティシアは一晩中泣き明かすのだった。
旅立ちの朝。
ウェルドに到着したレティシアは、いつもの景色を違った面持ちで眺めていた。
過去を振り返っても仕方がない。
だから彼女は、いつもその時の全力で挑んできた。
恋も、冒険者としての仕事も。
甘い部分もあって、仲間の支えで成長してきたこともあったが。
仲間たちの顔が浮かんでは消え、最後にミケの顔が浮かんで、また少し涙腺が緩みそうになる。
これからも、悔いが残らないように、爪先を前に向けて、前を向いて歩いて行こう。
そう決意を新たにし、背筋を伸ばす。
「レティ!」
後ろから声をかけられ、振り返る。
馬車乗り場から、ルシェがこちらに向かって走ってくるところだった。
「ルシェ姉ちゃん、間に合ったのね!」
「ああ。数日しかマヒンダには居られないけどね」
「忙しいのね。もうちょっとゆっくりできればいいのに」
「仕方ないさ。冒険者なんてそんなもんでしょ」
まあね、とレティシアが返すと、ルシェは彼女の顔を覗き込んだ。
「……何かあったのかい?」
さすがに1日では晴れがひかなかった目元に、心配そうに尋ねるルシェ。
レティシアは苦笑した。
「継承祭でルシェ姉ちゃんと別れた後、色々あったのよ」
続きを話そうとしたところで、出航の汽笛が鳴る。
二人は慌てて船に乗り込んだ。
マヒンダへ向かう船の上。
一昨日、ルシェと別れてからのことを話したレティシアに、ルシェは苦笑した。
「泣き虫なのは昔から変わらないねぇ」
「もう…いつまでも子ども扱いなんだから」
むう、とむくれるレティシアを、ルシェは妹を見るような慈愛に満ちた表情で見つめる。
「でも…レティシアが恋…ねぇ。チビだチビだと思ってたけど、大人になったんだねぇ」
「そうよ。私だってもう大人なんですからねー。実らなかったけど」
レティシアはおどけたようにそう言って、それから海へと視線を移す。
陽の光を反射して、キラキラ輝く水面は、これからの彼女の道を示しているような気がした。
「でも、自分の目指す道はみつかったから、ミケに会えた時に胸を張って会えるように、迷わずに進んでいこうと思う」
ルシェは黙ってレティシアの頭を撫でた。
昔の…子供の頃のように。
ずっとずっと好きだったの。 そのことに、後悔なんてしてないわ。 あなたに受け入れてはもらえなかったけれど。 そのことも丸ごと含めて、あなたのことが大好きな気持ちは変わらない。 だから、私はその気持ちを大切にしたまま。 私が見つけた未来への道を、一歩一歩歩いていく。
“Last Ceremony of Letisia Lude” 2021.1.17.Nagi Kirikawa