紅茶のセットを持ってきたレティシアは、少しだけ扉を開けて中を覗く。
そこには、すっかり見慣れてしまっ……嘘だ、見る度にときめく自分よりも長い髪の人物が机に向かっている背中が見える。
机と手の届くところに置かれた大きな本棚。部屋の中は、派手なものは何一つないのに、落ち着いた色合いの家具はしっかり作られた質の良いもので、ランプ一つとっても高価なのだろう。
ただ、それらが、とても落ち着く雰囲気でまとまっている。
窓から吹き込んでくる風も、穏やかで気持ちがいい。
そこに、そっと足を踏み入れる。
気が付かない部屋の主の近くのテーブルにそれを置き、そうっとそうっと傍に寄り。
「ミケ!お茶の時間よ!」
「っわぁ!?」
思い切り後ろから抱き付くと、青年はとても驚いた声をあげた。
「レ、レティシアさん!?」
「ぶぶー、もう一回」
笑ってそう伝えると、照れたようにふわっと笑って、レティ、と言い直した。恋人同士になったときに呼び名が愛称になったのだ。
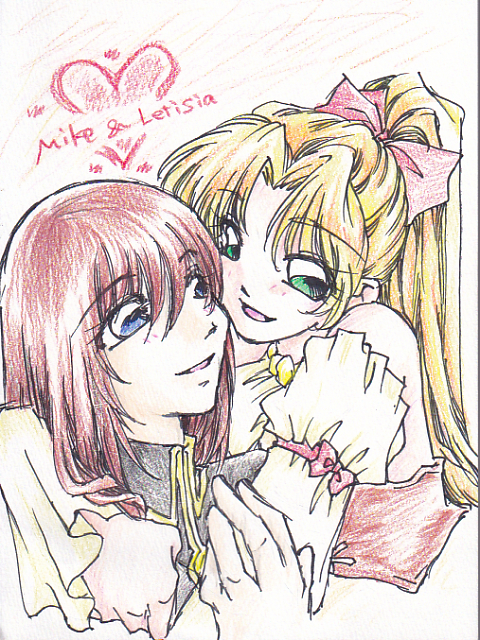
「あのね、お茶を入れてきたの。それにね、美味しいって評判のお店のクッキーをもらったからそれも一緒に」
「そうなんですか、それは、嬉しいですね」
「お仕事、邪魔だったかな?」
「いいえ。ちゃんと休憩しないと、効率悪いですから。あなたがちゃんと時間に声をかけてくれるから、助かります」
抱き付いた肩越しに覗き込むそこには、いくつかの開かれた専門書と新しい魔法の構築方法などが書かれている。
「凄いなぁ、ミケは」
「あははは、あなただって凄い魔導士じゃないですか」
「えええ」
自分も火属性の魔導士であるからわかっている。風の魔法を扱う目の前の人は、自分よりも遥か前を行く一流の風魔導士だと。
「最近、デスクワークが多いのね」
「ああ、そうですね。本当は現場も好きですけれど。元々冒険者ですし。でも、こう、少しギルドの中で地位をあげようと思うと、現場ばっかりじゃ駄目だと怒られまして」
あははと笑う、見た目物腰も穏やかな線の細いこの青年が、戦場の最前線で平然と荒事を行う苛烈な一面も持っている。
こうして部屋で本を読み、新たな術式を組み上げている方が似合いそうなものだが、全然関係のないアルバイトなどしながら、魔導士としての研究でちゃんと稼いでいなかったのは、かなり驚きでもあるが。
「でも、ミケ、強いのにねぇ」
「回復魔導士、現場ではかなり希少でしたけど……ギルドには貢献していないので」
「そ、そうね。でも、急にどうしたの?」
「ギルドに所属している場合ね、そこそこ実力があっても階級が上がらないと意外に仕事が回ってこないんですよ」
「うーん、私はほら、街の魔導士さん、みたいなところがあるから良く知らないのよね」
「僕もあんまり気にしていなかったところなんですけどね。今まではそれでも良かったんですけれど、そう言うわけにいかなくなったから」
偉くなっておくと、仕事のもらえる幅が広くなるので、と言う。
その言葉にレティシアは抱き付いたまま首を傾げる。
「僕、こう言ったらなんですけれど、魔族とか、下手したら凄い命の危険になりそうな冒険が多くて」
「ミケのトラブル引き寄せ率って、凄く高いよね」
「ううう、否定しにくい……それで、少し安全にお金を稼ごうと思ったら、もうちょっと階級が必要ですよと言われました」
大変だなぁ、とレティシアは思う。
全世界にまたがる魔導士ギルドに所属しているとはいえ、そちらで出世しようとは思っていない。レティシアが目指すのは、街の人たちと近い魔法使いだから。
「でも、向こうで真剣に出世しようとは思っていませんから、そこら辺はまだ楽ですけれどね」
「???」
「一軒家を買って、そこで魔法を使って生きていけるくらいの収入が欲しいんです」
「そうなのね。それで頑張ってるんだ……何か手伝えたらいいのに」
「僕は基本的に、これだと思ったら寝食忘れて突っ走るので、止めてくれるの、本当に嬉しいです」
「……」
こうしたい、とそう望んだなら、まっすぐにミケは走れる。その姿はたくさんの人を引っ張ったし、それを貫ける強さを眩しくも思った。
その反面、視野も狭くなることがあるから意見をする人も必要な時もある。それを聞いて議論する余地も持ち合わせているのは幸いだ。
「……私、ミケはもっと世界中回って色んなものを見たりして魔導士としての腕を高めるものかと思ってたのよ」
「ああ、それも機会があればやりますけれどね。定住しても腕を磨いたりは問題なくできると思います。……例えばヴィーダにも凄い魔導士がたくさんいますしね」
「うん、わかる」
「場所は特にこだわってなくて、故郷に帰ってもいいかなとも思いますし」
「むしろ、おうち買うって、地元に戻らなくていいの?」
「ねー、実家からも帰って来ればって言われてるんですよねー」
「……帰らないの?」
「別に帰ってもいいんですけどね」
困ったように笑うから、レティシアは不思議そうに見下ろす。
「ええとですね。あなたはこの後どうするんですかと相談したくて」
「私?」
「そうです。……あー、ええと、このタイミングで言うことになると思ってなかったから、どうしようかな」
するりと回りていた手を、上から握られる。
「ミケ?」
「あなたと一緒にいたいんです。あなたが街の人に近い魔導士になるのなら、その横にいたいし、どこかの街で定住するなら一緒に行こうと思っているんです」
「それって」
「あなたが故郷に帰るというなら、そこで家を買えばいいし。僕の故郷に来てくれるならそっちに戻る。幸いなことに、僕、これでも一流の風の魔導士ですから。もうちょっとだけ出世すれば、どこのギルドでもそれなりに仕事取れるので」
それは。
「指輪一つ用意してないの、申し訳ないんですけれど」
「ミケ」
「ねぇ、レティ。僕と結婚してくれませんか?あなたがいてくれると、そこはとても穏やかな風が吹いていて、落ち着くから」
「……はい、喜んで」
ぎゅう、と抱き付いてそう返事をする。
穏やかで優しいこの部屋は、そのままそっくり主の青年を写し取ったような空間だ。そこに自分の持ってきたティーセットが綺麗に馴染んでいる。
ふんわりと広がっている紅茶の香りも、全てが調和している。
それを彼も自分も心地よく感じて、幸せに思えるのなら。
これからもずっと、一緒にいても、こうして穏やかに過ごせるのだろうと確信できる。レティシアはドキドキしながら次の青年の行動を待った。
「よし、じゃあささっと仕上げて提出しますね!」
「え、この状況でそうなるの!?」
「はい?」
「……いえ、いいの、ごめんね」
できたらもうちょっとイチャイチャしていたかったが、この辺の感じがミケらしいと言えばミケらしい。
「レティ、レティ、ちょっと腕の力を緩めてくれると嬉しいです」
「あっ、ご、ごめんなさいね!すぐ離れ」
力を抜いた腕を引かれて、バランスを崩してミケに倒れ込んで。
風の魔法が支えてくれたので、変な風に倒れることはなかったが、代わりに頬に柔らかいものが触れる。
「できたら、ちゃんと抱きしめたかったんですけれど……僕も男なので、自分で自分を信用できないので、これで終わりにします。全部終わったらデートしましょう!」
「は、はひ……」
「そしたら一緒に指輪を探して、買ってきましょう」
頑張りますね、といつものように柔らかく微笑んでから。
「でも、今は一緒にお茶しましょうか。冷めてしまいますし」
「温めるの、得意よ?」
「あはは、猫舌なので大丈夫です」
少し遅めのティータイムは、言葉も少なかったし砂糖もなかったのにとても甘かった。
あやせかりんさんへのお久しぶりなお誕生日プレゼントとして描きました。そこに、相川和泉さんが素敵な文章をつけてくださいました。なんとプロポーズですよ奥様!夜景の見えるレストランで指輪を差し出しながら…とかじゃないところがなんともミケさんぽいですね。
スケッチブックに描いて色鉛筆で色を塗ったものです。色鉛筆にしか出せない質感が…出せてる…といいな…w
かりんさん、お誕生日おめでとうございます。私達の気持ちを受け取っていただければ幸いですv